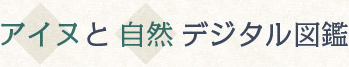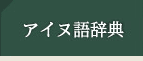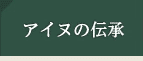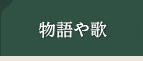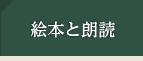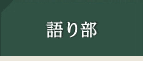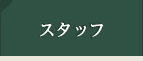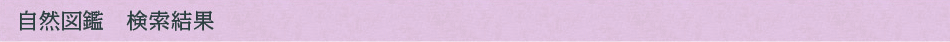日本語名:イケマ
アイヌ語名:イケマ、ペヌㇷ゚
利用:食用、薬用、祈り

イケマ
| 学名 | Cynanchum caudatum Maxim. |
|---|
| 科名 | ガガイモ科 |
|---|
| 種類 | つる植物 |
|---|
| 種ID | P0074 |
|---|
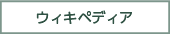
山地や林内の日の当たる場所に生えるガガイモ科のツル性多年草で、アイヌ語名も日本語名も「イケマ」といいます。夏に白く小さい花が丸くまとまって咲き、秋にはさやの中に綿毛のついた種子ができます。
アイヌ文化では根を焼く、煮るなどして食べますが、アルカロイドという毒が含まれている有毒植物なので注意が必要です。
また根を焼いたものは頭痛や打ち身の薬として湿布に使います。これには血止めの効果もあるといいます。煮汁は腹痛の薬にもします。
根の独特な臭気に魔をはらう力があると考えられ、輪切りを身につけてお守りにしたり、おまじないに使ったり、生活の中で清めが必要な場合に広く使われました。

イケマの実
アイヌ語辞典
植物編:植074(1)
アイヌ語名:イケマ ikema
語義:[i(それ)-kema(の足)]
地域・文献:⦅日常語――北海道・樺太⦆
区分:根
アイヌの伝承
アイヌ語での呼び方:イケマ ペヌㇷ゜
・根を焼いて皮をむいて食べました。34178
・根を干して保存しておき、お酒を作るときに魔よけのために酒の入った容器のふたの上に置きます。お葬式に行くときや、子供がお使いに出されるとき身につけます。おはらいのときは、かんで呼気を吹きつけました。34178