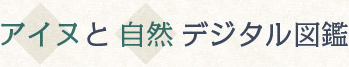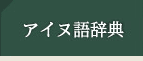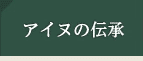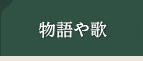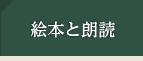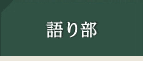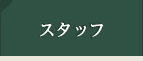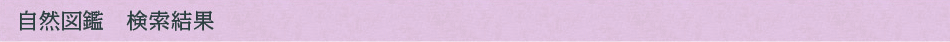分類辞典ではザゼンソウ、ヒメザゼンソウは同じ項目となっていますが、当館の採録資料では両種について別名が採録され、別種として認識されることがあるというのが判明しました。ザゼンソウの開花期は早春で花も目立ちますが、ヒメザゼンソウの開花期は初夏、葉が枯れてしまってからという違いがあります。
湿原で早春に生育する同じサトイモ科多年草のミズバショウ、ザゼンソウ、ヒメザゼンソウは、冬眠明けのクマが好んで食用にしますが、有毒植物であり、保存処理をしてアイヌが食用にするのはヒメザゼンソウだけで、他の2種を人が食べることはできないということです。ただしヒメザゼンソウも他の2種と同様にシュウ酸カルシウムなどを含むので、生のままやゆでただけで食べることは危険です。正しくはゆでてから干して保存したものを水につけてもどし、加熱調理して食べます。この過程で毒の成分が抜け、甘くおいしくなるのです。そのヒメザゼンソウは、同じくクマが好んで食べるオオハナウドとともに特に「神(クマ)の野草」といわれ、保存して常備しておき、儀式のときに供物として神に捧げます(日高地方)。

採取時期のヒメザゼンソウ
アイヌ語辞典
アイヌの伝承
アイヌ語での呼び方:パラキナ(=ザゼンソウ)、シケㇾペキナ(=ヒメザゼンソウ)
・ザゼンソウはクマのごちそうです(人は食べません)。
・ヒメザゼンソウは葉をゆでてから干して保存しておきました。「神の山菜」といわれ、人間が儀式をするために天から降ろされた野草だといいます。伝染病の神をよそへ送る儀式のときなどに、供物のひとつとして神に捧げました。34124(34138,34178,34181,34182)
・ヒメザゼンソウ食べるときは水でもどし、干したキハダの実を刻み、その汁に油や塩を入れ、そこへ刻んだヒメザゼンソウを入れて弱火で煮て味がしみてから食べました。34181
・ヒメザゼンソウは飼いグマにも食べさせました。34181