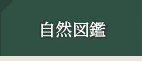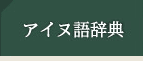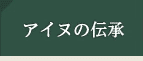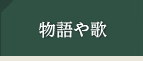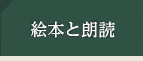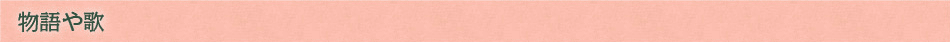ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
C0069. オオカミ神の娘がポイヤウンペの息子を育てる
あらすじ
私は天のオオカミ神の娘だ。父は人間界を守る役割を負っていたが、このごろは息子である兄に仕事を譲って隠居しているらしい。神々が集って四方山話をするが、それを聞いていると神々同士の話題ではなく、ポイヤウンペという人間のことばかりが話題に出て、その勇敢さ妻の美貌に感心して話し込んでいる。人間など、いかに勇敢で美しかろうとそれらはもとカムイが与えたものなのに、カムイ(神)ともあろう者達が何を気後れしているのかと思うと、腹立たしかった。そこでポイヤウンペのところに行って食い殺してやろうと思った。
父にはそんな私の考えがわかったらしく、兄に「娘が恐ろしい考えを抱いているようなので遠ざけねばならない。海のずっと向こうの果て、空が地にささるところに家をつくれ」と命じているのが聞こえた。兄は言われたとおりに、地の果てに立派な家を建てて戻ってきた。父は喜んで「息子は私の言いつけを聞いて一生懸命に家を作った。それではそこにお前の妹を連れて行きなさい」と言っているのが聞こえた。なんとしてもポイヤウンペを殺してやろうと心に決めて、その晩はすぐに寝た。
次の朝、早くに起きて炊事をし親たちに食事をさせると、兄が私を連れに来たので、色々私の使う家財などを持てるだけの荷物にまとめた。その大荷物を持って兄とともに海の果てまで入って見ると、思いがけず素晴らしい、父の家よりも立派な家だった。感激して兄に感謝すると、兄も喜んで「それでは私は人間界を見守る仕事に戻るから、決して悪い心を持つなよ」と言って帰っていった。
それでもポイヤウンペがどれほどの勇者だろうと、骨ごと食い殺してやろうと思い、ポイヤウンペの城まで出かけていった。すると、神々がうわさする者だけのことはあり、うかつに行くと殺されそうだった。昼のうちに近づくとすぐに殺されそうなので、夜を待ってひっそりと城へ行き、様子をうかがうと、ポイヤウンペ達は寝ているらしかった。そこで密かに火を点けて回り、やがて城が火に包まれて燃え落ちると安堵してうれしくなった。笑みを浮かべながら立って見ていると、どこかから赤ん坊の泣く声が聞こえてきた。声の出所を探ると、ヌサコㇿカムイの祭壇に盛った糠塚の中から聞こえてくる。糠を掘ってみると、おしめに包んだ小さな赤ん坊が隠されていた。ポイヤウンペの子どもだろうから食ってやろうと思ったが、あまりに小さいので育てて大きくしてから食べようと連れ帰った。お腹をすかせて泣けば何か作って食べさせ、ようやく這ったり歩いたりできるほどになった。
(ポイヤウンペの息子が語る)
私はどのようにして生まれたものなのだろう。物心ついて寝床から起き、炉端に座ってみると、私を育てている姉は、顔に二つの星があるようなギラギラ光る目をしており、口は耳元まで避けて、手や足は鍋のふたのように大きい。自分の手足と見比べても違うので「これが人間なんだろうか」と思っていた。立っても座っても、いつでも宝刀を身につけていて、鞘尻を引きずって歩いていた。恐ろしい形相をしていた。私に話しかけるときも、口が耳元まで避けているので、いかにも恐ろしいような形相だったが、幼かった私はそれが普通だと思って気にしなかった。ひとりで遊んで、お腹がすくと何か食べさせてもらい、お腹いっぱいになるとまた転げまわって遊んで寝た。
物事がわかってくると、姉は、私がポインヤウンペの子供であること、神々の評判に腹を立てて父の城に火をつけて焼き殺し、そのときに私を連れてきたことを言い聞かせ、自分よりも強い者はいないと言っていた。父の持っていた、神の鎧を兜や刀と一緒にしばって、父の城からずっと山手に行ったところにある大きな蝦夷松に吊り下げたと言っていた。姉は山へ行くと、冬は雪にさらされ、夏は雨にさらされ、木の上で揺れながらも落ちずにあるのを見て、父を殺したことを思い起こしては満足し、それから鹿や熊を獲って私に食べさせていたという。幼い頃はそのようなことを聞いても何とも思わずにいたが、やがて、姉が自分の両親を殺してやったと自慢して悦に入っているのだとわかってきた。
それから、何とか陸地にたどりつけるように密かに火のカムイやほかの神々に祈っていた。姉は山へ行くと2日3日帰らず、帰る時にはたくさんの獲物を背負ってきた。私には肉ばかりを食べさせ、自分は別の鍋で熊の骨だの、骨ばかりを炊いて、恐ろしい音を立てて骨を食べていた。歯が折れないのだろうかと思って恐ろしかった。話すときに姉の避けた口が開くのも、星のようなギラつく目も恐ろしかったが、そんなそぶりも見せないようにしていた。姉は料理をすると「早く食べろ、早く大きくなれ」と言って、自分は骨ばかり食べていた。
若者にまで成長すると、自分はどのような場所で育てられているのか気になった。姉が山へ出かけた後に外に出てみると、海の果ての空が地にささるところに大きな石があり、その上にいたのだった。あたりの海は青々として、波がかぶさると押し流されそうな、恐ろしげなところだった。家に戻ると、床も壁も屋根も、全部石でできた家だった。
ある晩、食事を終えると、姉が「明日はまた山に行かないと、もう食べるものがない」といった。私が「姉さんも年をとったし、自分も成長したのだから一緒に連れていって、狩りを教えてほしい」というと「まだまだお前は小さい。私はいつも、海の上に金の細橋をかけて爪先で渡って行き来しているのだ。お前が足を踏み外し、私が助けようとしたら二人とも死んでしまう。もう少し大きくなるまで待て」と言われた。しかし、なおも笑顔で頼み続けると、とうとう姉も承知した。
箱を出してきて神々しい着物を取り出し、私に着せた。我ながら人間とは思えないほど神々しい姿になった。姉は「明日になったら狩の仕方を教えるからはやく寝なさい」というので、喜んで床についた。翌朝食事を済ませると、姉は先に外に出た。そして「この金の細橋を爪先で渡るのだ。弟よお前には無理だから、危ないから帰れ」と言ったが、大丈夫だと言いはった。姉が橋を渡る後からついて行き、わざと姉のかかとをふんずけながら歩いたので「そんなに急いでは危ない」と言われた。そうしているうちに陸地にたどりついた。山や木を初めて目にして、いろいろ姉に聞きながら歩いた。鹿や熊も見た。姉は「角のある鹿がおいしいから初めにそれを獲って今晩食べよう」というと、あっというまに鹿を獲った。陸地に来たらなんとか逃げ出そうと思っていたが、驚いた。姉は「解体を手伝いなさい。山の上に狩小屋があるから今晩はそこで休もう」というので、私は急に腹が痛くなってものかげに行くふりをしてそこから離れた。そして、姉の狩小屋を見に行くと、とても大きな狩小屋がって、そこらじゅうに鹿だのの骨が食い散らかしてあった。
小屋のまわりにブドウの蔓がたくさんあったので、それを切って戸口と神窓、横窓をふさげるようにしておいた。戸口のそばにあった木やコクワの蔓も切って、戸口の前に山にして、それから姉の所にもどった。解体はすっかり終わっていて、姉は「腹が痛くてこんなに遅かったのか。足の一本でも手伝って運びなさい」といったが、腹が痛くてだめだ、といった。狩小屋に行き、焼き串を作って中に入ると、姉は大きな火を焚いていた。私は「鹿肉を焼いて食べたらおいしい、炊くよりも焼いて食べたい」といって、たくさん焼き串を作ってあったので、肉を刺してどんどん焼いた。「さあ、姐さん食べて食べて」と言って焼けたところを渡した。またどんどん焼いて「私はひと串食べれば十分だから、姉さんどんどん食べて」と言っているうちに、大きな鹿肉をすべて食べてしまった。
姉は満腹になって眠くなってきたらしく、片方の目をつぶり片方の目で私を見張っているが、そのうち腕を枕にして横になった。私は拍子木をつくって、炉縁を叩いてユカラ(英雄の物語)を始めた。合間合間に姉が笑って、耳元まで口が開くのを見ながら夜通し姉にユカラを聞かせていると、真夜中を過ぎて朝が近くなった頃、姉はすっかり寝てしまった。そこでそっと抜け出して、戸口をブドウヅルで塞ぎ、どうやっても出られないようにした。横窓も神窓もふさいで、がんじがらめに縛って、小屋のまわりに火をつけた。それから大木のカムイのところへいって、木にしがみつき、これまでの事情を話し、もし悪いカムイが死なずに追ってきても守ってくれるよう必死に頼んだ。
すると姉が「大変だ、坊や坊や家が燃えてるよ、坊やおまえ逃げたか」と必死に叫ぶのが聞こえてきた。小屋の屋根が焼け落ちた音が響くと、あの細い橋の上を「坊や逃げたか」と叫びながら行くのが聞こえたが、そのうち家までたどり着いたのか声も聞きとれなくなった。恐ろしくてひどく震えていたが、家までもどっていった様子を聞いてほっとした。そこに座りこんで泣きながら、両親のこともわからない、生まれた場所も知らないと言っているうちに父の鎧のことを思い出した。その鎧を探して、木の梢を見まわしながら行くうちに、とてもとても大きな蝦夷松を見つけた。天に届くような大蝦夷松で、そのてっぺんには確かに父の鎧と刀が光っていた。鳥のように蝦夷松の梢まで飛び上り、綱を切って鎧を持って飛び降りた。泣きながら「父さん母さんを殺した悪いオオカミの女を焼き殺してやりました。神々よ、父たちがどこかにいるのならそこへ連れて行って下さい」と言って泣きながら鎧を身につけ、川沿いに歩いて行った。とポイヤウンペの息子が語った。
本文ここまで
ここからフッターメニュー