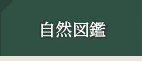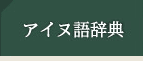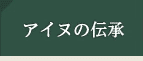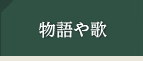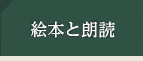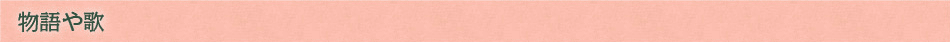ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
C0161. おばあちゃんとヤマブドウ
あらすじ
私は一人で祖母に育てられていた。祖母はなぜかいつも歌いながら家事をしていた。物心ついてからわかったのだが、歌っていると思ったのは泣いていたのだった。祖母を手伝えるくらい成長すると、小さな桶を作ってもらって、それで水汲みをして祖母を手伝った。祖母の飲み水も汲んで手渡してやると「ああ、私一人が生きていてお前の汲んだ水を飲めるんだなあ」というので、どうしてそんなことを言うのか不思議に思っていた。
あるとき、大きな荷物をしょった者が来た。祖母以外に人を見たこともなかったが、男というものらしい者が来て「しばらく来なかったが大きくなったなあ」といって私をかわいがった。恐ろしくて逃げようとするが「私はお前のおじだ。恐がるな恐がるな」という。そこへ祖母が帰ってきたので、おじがしょってきた食べ物などを祖母に渡すと、祖母は何度も感謝した。
おじが帰った後祖母はこういう話をした。「今までお前が幼すぎて話すこともできないでいたが、お前には両親がいたのだ。あるとき父親が山に入ったままもどらなかった。母親は心配して探しに行ったが戻らなかった。それで私一人でお前を育てていたのだが、あのおじさんはお前の母の弟で、上の村に住んでいてお前が小さい頃から食べ物を運んでくれていた。お前の両親が作っていた保存食もあるから、それで食べることに困らずにいるんだよ。それから、うちの上手にあるブドウの木も、育ちやすいようにいつも周りを手入れしているので、秋になると甘いブドウがたくさん実って、冬中食べることができるんだよ。これからおじさんが来ても恐がらないでお父さんみたいに思いなさい。」と言われたが、気にもせずにいた。
そうして、食べるものにも薪にも困らないのだが、祖母はなぜか私を置いて山に入る。どうしてだろうと思っているうちに秋になり、ブドウの実がたくさん実った。祖母は「手が届くものを採って食べなさい」というが、食べたこともないので食べないでいると、自分でも食べて見せて「食べ物なんだよ。さあ食べなさい」というので食べてみると本当に甘くておいしいものだった。それから祖母が山に行ってさびしい時にはそれを食べながら遊んだ。
大きくなると、家事でも何でも私がやった。祖母はいよいよ年をとって動くのもゆっくりになっていた。夜に水を汲むと濁りやすいので、いつも昼のうちに樽をいっぱいにしておいた。あるとき、水を汲みに川へ下がっていくと、下手の向こう岸に何か黒くて大きな者が来た。のろのろと動いて見えるそれでいて素早い変な者だった。川を渡ってこちらへ来ると、草藁の中に消えた。祖母に知らせなければと思ってすぐに家に戻った。
祖母にいま見た事を伝えると、身体を起こすのも辛そうなほど弱っていた祖母が、急にしゃっきりと座りなおした。「なんてことだ。今までお前が幼すぎて話すこともできないでいたが、あれを見たなら言わなければならない。お前には両親もおじいさんもいたのだ。上手の村に暮らしていて、私たちには一人しか子供がいなかったが、おじいさんは誰よりも狩が上手で、村の人々に獲物を分けるので、村長以上に頼りにされていた。そこの村長は心の悪いもので、おじいさんの評判をねたんで、悪いカムイに祈っていたらしい。お前の父さんも刈に行くようになると、誰にも劣らずよく狩りをした。新しい狩場も手に入ったのだが、そのうち元気がなくなり疲れた顔をして帰ってくるようなった。そのうちおじいさんは、悪いカムイに目をつけられたようなので、違うところに家を作ろうといって、ここに移ってきたのだ。おじいさんは他の村人が悪い長に目をつけられないよう付き合いを断っていたが、あるとき女の人が父親と一緒に来て、お前の父さんと結婚したのだ。そして生まれたのがお前なのだ。
お前の父さんは『自分一人で狩りに行っても食べることはできる。二人で狩りに行って、もし一度に悪いカムイに取られてしまったら家族が困るから』といって、おじいさんを家に残して山に入るようになった。一人でもたくさんの獲物を持って帰ってきたが、あるときお前の父さんが山に入ったままもどらなかった。おじいさんはたいそう心配してカムイに祈り、母親は心配して探しに行ったが戻らなかった。一晩待ってみたが戻らなかった。それでおじいさんは私に『何かあったに違いないから自分は行くが、お前はなんとしてもこの子を大きく育ててくれ。そうすればこの世にうちの血筋が残るのだから』と言って行ってしまった。私もお前を負って方々探してみたが、それきりおじいさんも戻らなかった。山で何か魔物に取られてしまったのだろう。
それからお前をひとりで育てて、家族を探したり、自分も死ねばまた家族で一緒になれるかと思って死のうとしたりもしたが、こらえて今まで暮らしてきたのだ。お前のおじいさんや父さんを妬んでいた悪者も、あるときふっと山に入って帰ってこなくなったという話だ。おじいさんと父さんが仕返ししたのだろう。
その、お前の家族を殺したものが、また今頃になってやってきたんだろう。私はもう年だから死んでもいい。お前は何とか生き延びて、上の村の人々に助けてもらって生きろ。そうすればお前のおじいさんや両親の血筋が続くんだから」といった。私は「おばあさんが死ぬなら自分も死ぬ」と言って泣いたが、祖母は私を叱って「明るいうちに食事を作りお腹いっぱい食べなさい。食べたら言うとおりにしなさい」という。
しかたなく炊事をしていると、祖母が外で何かしている。見に行くとブドウの蔓で輪を作っていて、私にその輪を持たせて家の周りを歩かせた。自分も一緒に歩きながら、輪を一つずつ家の壁に取り付けていった。神窓のところに来ると、ひさしの両側に輪をつけ、中窓も同じようにした。前小屋と母屋の戸は、その両脇に輪を取り付け、一つ余った輪は、梁に取り付けた。そしてご飯を食べたが、私は叱られても泣きながら食べていた。
食べ終わると、薪をたくさん入れろと言い、祖母は外からブドウを採るときのはしごを持って入った。家の中にはしごを立て、私に祖母の着物を1枚よこすと「梁の上にあがってこれを被って伏せてなさい。何があっても動いたり声を出したりしてはいけないよ」といった。言われた通りに上がって着物を被り、声を殺して泣きながら祖母がどうするのか見ていた。
祖母は寝床へ行くと、どこにしまっていたのか大きくて立派な槍を出した。その穂先を囲炉裏に入れ、上に薪を積んで大きな火をおこした。念入りに穂先を焼きながら、今度は着物を被って短い棒を持って戸口の上手側まで行き、短い杖をついてかすかにペウタンケしながら炉縁に沿って炉の角まで歩いて行った。また戸口に戻ると下手側からまた同じしぐさをした。
それが終わると着物をかけ、囲炉裏に戻るとさらに薪をくべて家中が明々と照らされるほど大きな火を焚いた。気が付くと辺りは真っ暗になっていて、どこかからバッタンバッタンと、よほど大きなものらしい重い足音が聞こえてた。家の中に入ってこようとして、前小屋の戸に引っかかってもがいている。それでも何とか入って来て、見ると大きな熊だった。大口を開け、前脚を伸ばしたのが見えた。そのとき、あの年を取った祖母が勢いよく飛び出し、その大口の真ん中に真っ赤に焼けた槍を突き立てた。ばちばちと焼ける音が聞こえ、熊は苦しさに両手を振り回した。そのとき、戸の両側につけていた輪に熊の前脚がはまり動けなくなった。熊があばれると、今度は梁につけた輪に上あごがはまり、熊は苦しさに大声を上げた。祖母も犬が遠吠えするようなすさまじい声でペウタンケし、家の中は騒然となった。祖母はぐいぐいと力いっぱい槍を突き入れ、ついに熊が力尽きて辺りが静かになった。
そこへ、上手の村の人々が駆けつけた。人々は熊を引きずり出すと、口々にののしって叩いたり蹴ったり大便小便をかけた。私のおじも来ていて、男なのに大声で泣きながら私たちの無事を喜んでくれた。一度村へ戻って食べ物を取ってくると、大鍋で料理をして、それを食べながら夜通し番をしてくれたので、私と祖母は安心して寝ることができた。朝になると村長が指揮して、皮のついたまま熊を切り刻んだ。熊の肉を絶対に口にしないように、指やナイフに付いたのを舐めてもだめだと注意しながら刻み、腐った木の株に撒き散らした。熊の頭は腐った木の株の上に置き去りにし、生き返れないようにした。
それから、2,3日は村の人が交代で泊まりに来てくれて、祖母が落ち着くのをまって村に移り住むように誘ってくれた。村長は「先代の村長は心がけが悪く人の富を憎んでは嫌がらせをしていた。あなた達は村長に憎まれて、呪いをかけられたのだろう。だが、今は自分が選ばれて村を治めているから、おばあさんも弱って子どもも幼い事だし、移って来ないか」と言った。祖母は祖父の建てた家に愛着があったが、移る事にした。祖父の家は、古くなったので「このままにして風で倒れでもすれば家の女神にも気の毒だ。食べ物とイナウをつけて燃やしてやれば、新たにカムイとなって先祖のところへ届き、先祖も暮らせるのだから」と言われたので、そのように祭って燃やした。
それからは、祖母も笑うようになり、村の上へ下へ遊びに行くようになった。もといたところのブドウの木はそれからも大切に手入れし、村の人たちがみんなブドウを食べるようになった。親切にしてくれた村長には、男の子二人、女の子一人があり、上の男の子はもう奥さんがいる年だった。皆にかわいがられて、私も「兄さん」「姉さん」と呼んでなついた。結婚してもいいくらい大きくなると、村長が祖母のところに来て「下の子と夫婦にさせよう」といってカムイに祈った。それからは夫婦になって、祖母に一生懸命孝行し、幸せな老後を送らせた。村中の人に親切にしてもらい、子供もできて、祖母ほどの年まではいかなかったが幸せな老後を送ってこの世を去るのだ。と一人の女が語った。
本文ここまで
ここからフッターメニュー