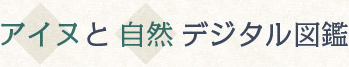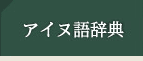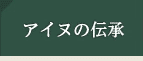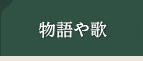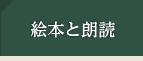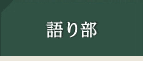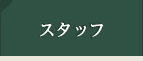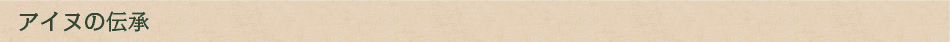| ID | 伝承者 | 日本語名 | 伝承者の アイヌ語名 /日本語名 |
伝承 |
|---|---|---|---|---|
| 1433 |
P0207 シウリ(シウリザクラ) |
【ア】シウリ |
・「シウリ」はアイヌ語ではないでしょうか。浜ではこの木で舟の櫂を作ります。スッとした軽い木です。 | |
| 1434 |
白老町 |
P0207 シウリ(シウリザクラ) |
【ア】シウリ |
・車櫂にするには一番いい木でした。30600 |
| 1435 |
 むかわ町
むかわ町 |
P0211 ハマナス(ハマナシ) |
【日】ハマナス |
・生の実を食べました。豚に食べさせたこともあります。35240,35247 |
| 1436 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0211 ハマナス(ハマナシ) |
【ア】マウ |
・子供の頃は山の方に住んでいて知りませんでしたが、浜に遊びに行ったときに食べられると教えてもらいました。生で丸のまま口に入れたところ中に綿がたくさんあり「これでは食べられない」と言うと、「その綿を取ってから食べるものだ」と言われました。34102 |
| 1437 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0221 シロワレモコウ ナガボノシロワレモコウ |
【ア】シッカㇻムン |
・アワの穂のように、実がついたら穂がたれてきます。目が痛かったり目やにが出たとき、おばあさんがこの葉をとってきてくれて、お湯に通してから目をぬぐってくれました。34101,34184 |
| 1438 |
P0221 シロワレモコウ ナガボノシロワレモコウ |
【ア】シッカㇻムン |
・目をぬぐうのに使うかも知れません。(アイヌ語名を聞いて、その意味からの口述) | |
| 1439 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0224 ノリウツギ(サビタ) |
【ア】ラスパニ |
・湿地に生えている木です。34178 ・昔の年寄りは、この木の枝をとり、針金で通してストロー状にし、キセルの吸い口を作っていました。たくさん作ってまとめて干しておき、吸い口が割れると新しいものにつけ替えていました。34103,34178 ・布の中に木の切れ端を入れてお湯につけるとネタネタして来ます。それで髪を洗いました。石けんで洗うと顔がつっぱりますが、この木で洗うとつっぱりませんでした。34103 ・乳腺炎のときなどに、木を削ったものをお湯に通し、しぼったもので湿布をしました。また膀胱の病気の人がこの木の枝をお湯で煮た汁を飲んでいました。34103,34178 |
| 1440 |
 平取町
平取町 |
P0224 ノリウツギ(サビタ) |
【日】サビタ |
・これで髪を洗います。35004 |
| 1441 |
平取町 |
P0224 ノリウツギ(サビタ) |
【ア】ラスパニ |
・この木で頭を洗いたいと思うことがあります。35268 |
| 1442 |
 平取町
平取町 |
P0235 センダイカブラ、センダイカブ(ルタバガ) |
【ア】アタネ 【日】センダイカブ |
・地下になる実の部分を四つ割りにし、炉の灰の中に入れて焼いて食べました。この焼く時のにおいを伝染病の神が嫌うといいます。実は赤と白の2種類があり、赤い方はおいしくありませんでした。お母さんはこの実の皮を剥くと、必ず炉の下手で燃えているまきの間に挟みました。34605(34640,34713) |
ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
本文ここまで
ここからフッターメニュー