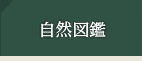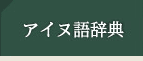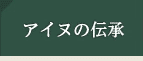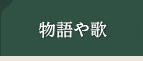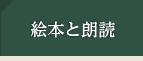植物編 §080 アオダモ Fraxinus Sieboldiana Bl.
iwani イワニ [iwa(山地)ni(木)] 茎 ⦅全北海道⦆
(参考1)この木は弓・器具の柄・焚き木などに用いた(幌別)。よく燃えるので山の神の松明などとも言われた(白老)。皮を取って水に入れると青くなるので、その木を染料に使った(屈斜路―D、p.7)。標茶・塘路付近のアイヌはオヒョウの皮をはいで温泉に入れて漂白し、それをタモの木とハンの木で染めるとあるが(河野広道、アイヌの織物染色法)、そのタモの木というのはアオダモのことではなかろうか。
この皮は文身(いれずみ)をする時の染汁を作るのにも用いた。文身をするには、まず適当な場所を選んで臨時の炉をつくる。入口の土間とか、天気のいい日なら戸外の風の当たらぬ場所とかを選び、ふだん物を煮炊きする屋内の炉は避ける。ただ、やむを得ない時にかぎり、屋内の炉の、ふだん火をたくことのない火尻の一隅を選んで、そこを清めて使うこともある。
炉が出来たら、その上に、小鍋に水を入れてかける。この小鍋は、あらかじめよく洗って鍋底の墨などはすっかり落としておく。
小鍋の中には、水だけのこともあるが、多くは、アオダモやヤチダモの皮を刻んで入れたり、まれにはミズキ、クロウメモドキ、クワなどの皮、あるいはヨモギの葉、ハマナスの根などを入れたりする。千歳では、黒豆を入れたという例もある(児玉作左衛門・伊藤昌一、アイヌの文身の研究)。
幌別では、エゾニワトコの年内に伸びた若枝を9cm位に切っていれた。
これらの材料は、鍋の中で煮立てずに、別の容器に入れておいて、小鍋の湯が煮立った時に、それへ注いで浸出液をつくることもある。その液汁を「ペエ」(pe-e 物の汁)「ペヘ」(pe-he 同前)、「ペエ・ワッカ」(pee-wakka 物の汁・水)と称する。この液汁は、後に手術部位の消毒や血止めに用いる。
小鍋を沸かすには、北海道でも樺太でも、一般にシラカンバの皮を焚く。この皮は火をつけると黒煙をあげて燃え、小鍋の底にまっ黒な油煙をつける。この油煙は、文身の染料に用いるためのものである。
幌別では、シラカンバの油煙は、傷の治りがよくないと言って、ホオノキやノリウツギの枯れ枝を焚いて油煙をつくる者もあった。
この鍋底についた油煙を、「シュパㇱ」(su-pas 鍋・墨)という。日高のある地方では、黒曜石のような綺麗な石をよく洗って、まだ濡れているうちに炉にかけて、下からシラカンバの皮を焚いて油煙を取った(児玉・伊藤、上掲論文)。それを「シュマパㇱ」(suma-pas 石の・墨)と言った。
文身を施す際は、施術者は被術者と向かい合って座る。被術者を仰向けに寝かせることもある。施術者は、まず黒木綿の小片を前記の液汁の中に浸して、それで施術しようとする部位をていねいに拭う。ヨモギの葉の浸出液(「ノヤペヘ」noya-pehe ヨモギ・の汁)を用いる場合は、直接ヨモギの葉を液の中から取り出して、それで拭う。それから、指先に鍋底の油煙をつけて、それで文身を施そうとする部位に、模様の下書きをする。そしてその上を刃物の先で横に小さな浅い傷を無数につけて行く。その際に使う刃物としては、北海道南西部ではカミソリ、中東部では「エピラ」(epira)と称する先の細い小刀、樺太でも「エピリケㇸ」(epirikeh)と称する同様の小刀を用い、いずれの場合でも布で巻いて先だけ出しておく。「エピラ」も「エピリケㇸ」も同じく「それで傷をつけるもの」の意味である。辞書に「アンチピリ」“文身の痕跡”とあるが、anci-piriは“黒曜石・の傷”の意味であるから、昔は黒曜石の小刀の先で文身の傷をつけたのである(→参考2)。この刃物は時々前述の浸出液に浸しながら使う。また、傷から浸み出る血をもそれでぬぐい、そのたびに油煙をすり込んで血が止まるまでそれを繰り返して行くのである。この浸出液にアオダモの皮を刻んで入れるのは、黒豆を入れたり、黒木綿の小布を使ったりするのと同じく、文身の色を濃くしようとする意図に出たものであろう。
(参考2)前文で文身のことを説いた際、それに関連して黒曜石の小刀に言及したが、ついでにそのことをもう少し詳しく述べておこう。
小刀を意味する語は種々あるが、その中で最も普通なのは makiri という語である。この語は、もともと物と共に日本内地から北海道に持ち込まれ、漁場請負制度の発達と共にアイヌの間に普及したのであって、北海道はもちろんのこと、樺太、千島のアイヌにも用いられ、遠くアレウトの語彙にまで取り入れられている。しかし、この語が千島に入ったのは、そんなに古いことではない。明治32年(1899 A.D.)に鳥居龍蔵博士が北千島のアイヌを調査された際、彼らは小刀をeperanikiと言っていたとある(千島アイヌ、p.147)。それはしかし鳥居博士の誤解で、eperanikiは単語ではなくて、おそらく“epera ani ke”「小刀、をもって、掻く」という文だったと思われるから、小刀を意味する千島アイヌ語は、eperaだったに違いない。――ついでながら、小刀はもと“切る”ものではなく“掻く”ものだったらしい。木を削ってイナウ(削り花)を作ることも“inaw ke”「削り花を掻く」という言い方をするのである。これは、後に説くように、アイヌの小刀が最近まで黒曜石などの砕片で作られた石包丁だったことと大いに関係があるのである。
千島アイヌは、「エペラ」の他に、「マキリ」という語も知っていたが、それについては北海道のアイヌ語だという明らかな意識を持っていた。“Makiriとも云へどこれは蝦夷アイヌ語なりと云ふ”と鳥居博士は報じておられる(前掲書p.147)。
ところが北海道のオホーツク海沿岸に来ると、斜里でも網走でもepiraという語があって、古老はそれを古語として記憶している。海岸から奥地へ入って、屈斜路や足寄あたりへ来ると、「マキリ」というのは日本人のことばで、それが流行しだしたのは今いる古老の少年の頃からであり、その頃は「エピラ」という語を日常使ったという。
北海道も南の方、日高や胆振へ来ると、もっぱら「マキリ」だけが記憶され、そこのアイヌはそれを固有語だと主張してやまない。しかしながら、寛政3年(1791)に菅江真澄が虻田でエピラという語を拾い上げているから(『蝦夷迺天布利』)、この地方でも約160年以前にはエピラという語が用いられていたことが分かるのである。
古い文献、例えば寛永7年(1630)の蝦夷談筆記上巻、正徳5年(1713)の松前志摩守差出候書付などには、小刀を「エイワケ」「エイワキ」としてある。eiwanke-p“使用する・もの”であろう。享保5年(1720)の蝦夷志には伊牙烈布(イケレッフ)とある。i-kewre-p“物を・削る・もの”の義であろう。その他、蝦夷記という本には短刀をエヒリケとしている。これは明らかにe-pir-ke-p“それで・pir(傷)・掻く・もの”の義であって、今でも樺太アイヌは「エピリケㇸ」と言って、女持ちの細い小刀を称している。
epira、eperaなども、それと同じく、e-pir-a-p“それによって・pir(きず)・つく・もの”、あるいは e-per-a-p “それによって・per(裂け)が・つく・もの”の義だったと考えられる。傷を意味する pir は、もともと per(裂け)から来た語であって、本来は裂け傷を意味したらしい。それは鉄製のマキリですうっと切った傷ではなくて、石包丁などでごしごし擦ったり掻いたりした傷であったと思われる。先に挙げた i-kewre-p “物を・削る・もの”の kewre(削る)なども、すうっすうっと削ることではなく、ごりごりがりがり掻き削ることである。epera、epira、epirikeh はもとはそのような刃物だったのであって、もとは石包丁であったに違いないことは、名称の上からも察しられるのである。
木幣なども、今のような kike-parse-inaw(削り掛けが・ばらばらに垂れた・幣)とか kike-cinoye-inaw(削り掛けを・撚った・幣)とかが出来たのは、鉄製の小刀、すなわち「マキリ」が入ってからであって、それ以前はもっぱら棒幣であり、それは棒に石包丁の刃を直角に当てて引き掻き、数カ所に掻き綿の小塊をつけたものであったと考えられる。そのような方法で作った掻き綿を、北海道ではni-mawまたは単にmaw、樺太ではro-ciと言って、われわれにおけるタオルやガーゼや脱脂綿のごとく、湿布ぎれに用いたり出血の場所に当てて包帯したりするのに用いる。それは古い時代の幣と幣作りの技法の残存である。幣を作ることを“inaw-ke”「幣を・掻く」というのも、その古い技法を示すものであり、また削り掛けをinaw-kikeというのも、語源はinaw-ke-ike“幣を・掻いた・もの”の義であって、やはり上記の推測を裏書きするものである。
マキリはもともと日本渡来の鉄製の小刀であった。それは最初漁場で魚を処理するのに用いられた。当時の漁場の労働力はほとんどアイヌであったから、それらのアイヌが漁季すぎて帰郷する際、それを自分の村に持ち帰ったのであろう。このようにしてマキリはアイヌに普及したけれども、それでも漁場に遠い奥地では、比較的近い頃まで石の小刀、すなわちエピラまたはエピリケㇷ゚を使っていたらしい。バチラー博士が十勝で一人の老婆に会った際、彼女は文身をさして「アンチピリ」と言ったという。anci-piriは“黒曜石の傷”ということであるから、そう古くない頃まであの地方では黒曜石の小刀を使って文身を施していたことが分かるのである。
それではその黒曜石の小刀とは、どのような形状のものであったろうか。
樺太で「エピリケㇸ」と言っているのは、すでに述べたように、女持ちの細い小刀である。それが一層細くなって、針のようになったものに「ケメピリケㇸ」(kem-epirikeh「針の・傷をつけるもの」)と称する小刀があって、これは神話に出てくる「オヤシ・イコンノ」(oyasi-ikonno「ばけもの・婆」)の腰に下げる物とされている。おそらくそれが化け物婆の腰にぶらさがる以前は、アイヌのメノコの腰に下げられていたのであろう。そして文身を施す際は、その細くとがった先を利用して、皮膚に浅い裂き傷を無数に作ったにちがいないのである。