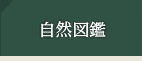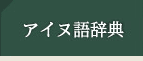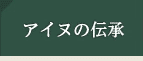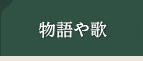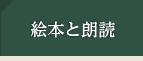植物編 §338 オオウバユリ エゾウバユリ Cardiocrinum Glehni Makino
(1)turep トゥレㇷ゚ [<ru(とける)-re(させる)-p(もの)、→注1] 鱗茎 ⦅北海道全地⦆
注1.――tureh(<turep)という語は、樺太では、「木の実」を意味する。北海道でも、桑の実に限ってturepと言った例がある。§296、注1、参照。樺太では、オオイタドリやウラジロタデの若い茎を、食用土を溶かした水でどろどろになるまで煮て、さらにそれを木鉢の中ですり潰して、それに獣油あるいは魚油を注いでかき回して食べる料理があり、それを「イルレㇸ・チカリペ」(イルレㇸ・料理)という(→§284)。「イルレㇸ」というのは、この料理に使うオオイタドリやウロジロタデの若い茎をさす(→§284、287)。語源はi(それを)-ru-re(とか・す)-p(もの)かと思われる。このi-ru-re-pが、i-rurep(それの・ルレㇷ゚)となり、さらにturep、turehになったのではなかろうか。木の実でも、turepと言われるものは漿果が多く、樺太ではそれを秋に採集して冬に凍っているのを溶かして使うものが多く、また堅果でも搗いて水に溶かして澱粉をとるものが多い。要するに、果実でも、茎でも、根でも、溶かすものがturepなのではなかろうか。
注2.――菅江真澄は「ルレップ」(オオウバユリ)という形を採録している。
(2)putput プップッ 花茎 ⦅幌別⦆
(3)erapas エラパㇱ 鱗茎 ⦅白浦⦆
(4)kiw キウ 鱗茎 ⦅真岡⦆
(5)anrakor アンラコㇽ [an(黒い)ra(葉)kor(持つ)] 地上に出たばかりの若い葉 ⦅穂別⦆
注3.――anrakorという語は、普通クロユリの鱗茎をさす(→§342)。しかし、語源は「黒い・葉を・持つ」ということだから、オオウバユリの地上に出たばかりの黒っぽい葉をさしても不思議はない。なお、ウスバサイシンをさすこともある(→§290)。
(6)『ハル』 [haru 食糧] ⦅千島⦆
注4.――鳥居龍蔵博士の『千島アイヌ』に“ウバ百合 haru”とあり(p.171)、また“ハルとは百合のことにてハルムコタンとは百合多くある所と言える意味なり”とある(p.43)。千島アイヌ語ではオオウバユリの鱗茎をharuと言ったのである。
(参考1)6月末から7月初めにかけて、鱗茎を掘って来て、そのまま炉の熱灰の中に埋けて焼いて食べたり、よく洗って細かく刻んで「サヨ」sayo[かゆのこと、日本語の「白湯」から来た]の中に炊き込んで「アフンパ・トゥレㇷ゚・サヨ」[a(我ら)-humpa(刻んだ)-turep(ウバユリ根)-sayo(かゆ)]にしたり、細かく刻んだのを生干しにして臼で搗き、円盤状に丸めて干し固めたりした。この干し固めた円盤状のものを「トゥレパカㇺ」turep-akam[ウバユリ根・円盤]、あるいは一層正確には「オントゥレㇷ゚・アカㇺ」onturep-akam[風化したウバユリ根・円盤]と称し、冬になってから「オントゥレㇷ゚・サヨ」onturep-sayo[風化したウバユリ根・かゆ]などにして食べた(幌別)。
また、鱗茎をよく洗って臼に入れて搗き砕き、それを「イチャリ」icari[ざる、日本語の方言からきた]あるいは「サラニㇷ゚」saranip[こだし]に入れて、上から水を注いで漉し、その水を樽に溜めておくと、底に「イルㇷ゚」irup[“澱粉”、i(<eそこに)-ru(溶ける)-p(もの)]が沈殿する。この澱粉は、団子に丸めて焼いて食べたり、干して貯えておき、かゆに混ぜて「イルㇷ゚・サヨ」irup-sayo[澱粉・かゆ]にしたり、あるいは「くずかき」にしたりした。「くずかき」を幌別では「イルㇷ゚・テリ」irup-teri[澱粉・ねばねば]、美幌・屈斜路では「イルㇷ゚・ペネㇷ゚」irup-penep[澱粉の・汁になったもの]という。
澱粉を焼いて食べるには、適当に湿らせたものを、フキの葉・イタドリの葉・朴の葉等に包んで熱灰の中に埋けておく。朴の葉で包むのが最も上等とされている。
弁当を持たずに山へ行って空腹を覚えた時は、そこらからウバユリの鱗茎を探し出して来て、洗って、ナタの背などで叩き砕いて、それを上記の葉で包むか、あるいはウバユリの薹(とう=花茎)が見つかったら、その中へ詰めて、両端を結び、火を焚いてその熱灰の中に埋けて蒸し焼きにし、薹の外皮をむいてそのまま食べた(幌別)。
樺太では、この鱗茎を山から掘ってきて、よく洗って細かく刻み、「ライムン」ray-mun(テンキグサ)を敷いて、それにこの細かく刻んだものを入れて、すっかり包んで、半月ほど寝かせておく。この蓆包みは、戸外に棚を作ってその上に置き、雨水が入らないようにしておく。この過程を「オンカ」on-ka(風化・させる)という。半月ほどたったら、蓆包みを解いて、「オトカ」otoka(木製深鉢)に入れ、「イネナㇵ」inenah(すりこぎ)[i(それを)-nena(こねる、=北海道 nina)h(<p(もの)“それをこねるもの”]ですっかり潰して、それを円盤状に丸め、早く乾くように穴を五つくらい開けて、それをざるなどに並べ、天気のよい日は戸外で、その他は屋外の火棚の上に載せて干し固める。この干し固めた円盤状の食糧を「エラパㇱ・アカㇺ」erapas-akam[ウバユリ・円盤](白浦)、あるいは「キウ・タㇵペ」kiw-tahpe[ウバユリ・団塊]と称し、これは冬まで保存しておいて、冬になったら、いわゆる「エラパㇱ・チカリペ」erapas-cikaripe[ウバユリ・料理]を作る。
「エラパㇱ・チカリペ」の作り方は、まず、かんかんに乾いている「ウバユリ・円盤」を水の中に漬けておいて、その水を2回くらい取り替える。柔らかになったら、取り出して鍋に入れ、米を少量と、それに獣油または魚油を少量加えて煮る。すると、かゆ状のものになる。それを炉から下ろして、少し冷ましておいて、冷えた頃に、また油を入れて撹拌すると、あたかもかゆに澱粉を入れたようなおいしい物が出来ると言っている(白浦)。
天塩では、酒を造るのに、カツラの皮を煮て、その煮汁で飯を炊き、それに少量の麹を入れて、そのまま寝かせておくが、その際米が足りなければ、オオウバユリの鱗茎を煮て潰したものを入れて、酒の分量を増す。オオウバユリの鱗茎は、多量に採集してそれをざっとゆでてから乾かし、それに糸を通して保存しておき、必要の際に取り下ろして使うのである。その、ざっとゆでて干したものを、「チサカンケ・トゥレㇷ゚」ci-sakanke-turep[我ら・ゆでた・ウバユリ]という(名寄)。
オオウバユリの鱗茎を掘るには、特別の掘り棒を用意した。長万部では、それを「トゥレㇷ゚・タ・ウライニ」turep-ta-urayni[ウバユリ・掘る・簗木]と言い、長さ60cmくらいの棒で、先端を平たく薄く削る。美幌では「トゥレㇷ゚・タ・ニ」turep-ta-ni[ウバユリ・掘る・木]あるいは「トイオウリㇷ゚」toy-ouri-p[土・掘る・もの]と言い、イタヤあるいはその他の堅い木で作り、やはり先を平たくする。
なお、美幌では、ウバユリの根を搗くのに、「サマッキ・ニス」samakki-nisu[横になっている・臼]と、それから「トゥレㇷ゚・オッケ・ニ」turep-okke-ni[ウバユリ・突く・木]と称する特別の杵を使った。
(参考2)オオウバユリとギョウジャニンニクは「ハル・イッケウ」haru-ikkew(“食糧の・背骨”“食糧の中心になるもの”)だと言われる。太古、人間がまだ野草を食べることを知らなかった時代、これら野草が人間の国土の山野に、年々歳々採る人もなしに空しく咲いては散って、それらの霊魂が祭られることもなく泣きながら神の国へ引きあげて行くのを嘆いて、オオウバユリとギョウジャニンニクの頭領が人間の女に化けてウラㇱペッの酋長を訪ねて来る話がある。「ウラㇱペッ」[Uraspet、<uray(簗)-us(多き)-pet(川)]とは、北見のオホーツク沿岸に昔あったコタンで、そこの酋長たる「ウラㇱペトゥンクㇽ」(Uraspet-un-kut、→§144、参考3、参照)は、胆振・日高の説話にまでヒーローとなって出てくるほどに有名であった。次に掲げるものは、胆振国幌別の説話で、「ウウェペケㇽ」(uwepeker「伝説物語」)というジャンルに属するものである。
俺は立派な酋長で立派な妻を持ち仲良く暮らしていた。するとある日次のような噂が聞こえて来た。――東の方から、小さな女が小娘を連れて、村ごとに酋長の家を訪ねて泊まり込み、お椀を借りては物陰に行ってその中に脱糞し、酋長に食べて頂戴と言って差し出す。酋長が汚がって食べないと、ひどく怒って散々に罵倒しながらまた次の村へ来て、同じことを要求しつつ、今はもうこの村の近くへやって来ている――というのだった。もしそれが事実なら、俺の村だけ避けて行くわけはないと思ったので、俺は心の中で、火の媼神や家の神や憑き神たちに聞かせて、神様というものは何事でもご存知なのだから、噂の女どもがもしも悪性の者ならば、この村へは向けさせないでくれるようにと、ひたすら念じていた。妻も俺の身を案じて、ひどくしょげきっていた。
するとある日、戸外で犬の吠える声がした。妻が戸口へ出てからすぐ戻って来て、例の女どもがいよいよやって来たと告げた。それでは座席など整えてお入れ申せ、と俺が言うと、妻はいまいましげにざっと客席のちりを払ってから、女どもを案内して来た。見ればなるほど小さな女ではあったが、悪性の者とは更に見受けられず、続いて入って来た小娘と共に神貌をそなえているように思えた。左座に並んで座った。俺が会釈すると、2人ともひどく喜んで、炉の火に当たりながらよもやま話を始めた。聞いているとそれが皆神々の噂ばかりであった。
俺も良い話題ばかりを選んで話していると小女が話の隙をとらえて、お椀を貸して下され、という。貸してやると聞きしに違わず、物陰へ向いて何かごとごとしていたが、やがて大椀にいっぱい何かしらどろどろした変なものを入れて、俺の前へ差し出した。人間の汚物なら悪臭を発しそうなのに、悪臭どころか、うまそうなにおいがぷんぷん鼻をついた。押しいただいて食べてみると何とも言われぬ良い味。独りで食べるのも惜しいので、食べさしを妻に伸べると、妻も押しいただいて受け、大変うまそうに食べたのであった。それを見た女たちは非常に喜んで、にこにこしながら歓談を交え、やがて妻が敷いた花ござの寝床に入るのだった。
俺たちも良い気持ちで寝につくと、いつかぐっすり寝入ってしまった。すると、枕がみに先刻の女たちが立っていて、小女の言うことはこうだった。
「これウラㇱペッの酋長どの、よく聞かれよ。私どもは人間でもなく、また悪神でもない。私はオオウバユリの頭領、これなるはギョウジャニンニクの頭領である。太古国造りの神が国土を造りたまいし時、人間の国土の表の、野にも山にも一面に、人間に食べさせようとて、木の実・草の葉・草の根など用意しておかれたのに、人間どもはその大部分が食べ物であることを知らない。中でもギョウジャニンニクとオオウバユリは食糧の中心だったのに、採る人もなしに、年々歳々人間の国土の山野に花を開いてはむなしく散って行く。そしてその霊魂が泣きながら神の国へ帰るのだ。それが悲しいので何とかしてオオウバユリもギョウジャニンニクも食べれるものだということを人間に教えて自らも神に祭られたいと思い、人間の女に化けてこれなるギョウジャニンニクの頭領と一緒に東の方から人間の国土をやって来たのだが、人間どもはあまりに愚かで、ただ汚いとばかり考えて私たちの食糧を試みに食べてみようともしない。それで憤慨しながら御身の所へ来たのだが、御身も私たちの食糧を食べない場合は、もはやこれまでと諦めて、一族を引き連れて神の国へ引き揚げようと決心していたのだ。しかるにさすがは代々音に響いていたウラㇱペッの酋長の裔だけあって、私たちの食糧を汚がりもせずに食べてくれた。心からありがたく思う。御身のおかげでこれからは神となれるのだ。オオウバユリの食糧やギョウジャニンニクの食糧の採取法調理法を御身は学んだのだから、今よりは遠い村近い村にもそれを伝えるがよい。ギョウジャニンニクの食糧を守護神として祭るならば、いかなる疾病にもかかることなく、子々孫々繁栄するであろう。御身はいと賢く、心もよいから、今より一層立派な首領になるであろう」
と言ったかと思えば夢さめたのであった。妻も同じ夢を見たのであった。最前の女たちの寝床を見ればもぬけのからだった。
そこで幾度も手を揉んで礼拝し、妻と共に里川に沿って行ってみると、言うがごとくオオウバユリと称するもの、ギョウジャニンニクと称するものが、地面を覆うて見渡す限り繁茂していた。そこで妻と一緒にコダシいっぱいオオウバユリの根やギョウジャニンニクを採って来て、オオウバユリの根は臼で搗いて澱粉を取り、残った粕は干して団子にした。そして村の人や遠い村近い村の人々にも教えたので、今では同族も異族もこれらの食糧を知って、大いに俺を徳としたのであった。神様も俺たちを見守って下さるとみえて、まるで何か上から降って来るように、限りなき長者となって、多くの子供を持ち孫を持ち、「どんな飢饉があっても疫病がはやっても、オオウバユリやギョウジャニンニクがあるおかげで、村が立って行くので、子々孫々に至るまで、ゆめゆめオオウバユリとギョウジャニンニクとを忘れず、食糧として暮らして行きなさい」と教訓しつつ今は極楽往生を遂げるのだ。――とウラㇱペッの酋長が物語った。