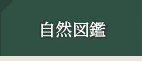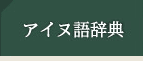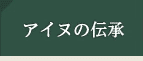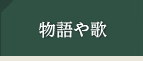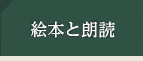ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
月刊シロㇿ 創刊号(2015.3)
今月の絵本1「スズメの恩返し」(川上まつ子さん伝承)
文:安田益穂
(毎月一話、「アイヌと自然デジタル図鑑」に収めた絵本をご紹介します)
語り手:川上まつ子さん(1912-1988)
絵:小笠原小夜
朗 読:今津朋子
音 楽:千葉伸彦
録音年月日:1985年5月7日
録音場所:アイヌ民族博物館
調査者:伊藤裕満(アイヌ民族博物館学芸員)
資料番号:34600A
語り手について
物語の語り部、川上まつ子さんは日高地方の平取町荷負生まれの伝承者で、アイヌ語をはじめ多くの研究者の調査に協力しました。アイヌ民族博物館では1983年から勤務し、聞き取り調査などに協力、146本の録音テープを遺しました。
この物語もその中の一つで、鳥のアイヌ語名や伝承についての調査の中で、「スズメが人間に祭られたウウェペケㇾ(節をつけずに語る物語)」として紹介しています。物語をまずアイヌ語で語った後、日本語で再び語り直しています。どちらも約12分の語りです。
 川上まつ子さん
川上まつ子さん
ストーリー
この物語の特徴を一言で言えば、ストーリーの面白さ。シナリオ学校の教材になっても良いぐらい(?)よく出来たストーリーです。しかもこの絵本の脚本は、川上まつ子さんの日本語語りほとんどそのままです。あえてドラマの構成にあてはめてみると、
| 【設定】 | 名もなく親もない平凡な主人公(子スズメ)が |
| 【対立】 | 未知の世界(アイヌの村)へ冒険 〜美しい人間の娘に出会い、助けられる 〜娘の死(暗転) 〜悪役登場 |
| 【解決】 | ユーモアで危機を解決 〜平凡な主人公が一躍ヒーローに 〜ハッピーエンド。 |
12分の短編ですが、笑いあり涙あり、ドラマに必要な要素がコンパクトに詰まった名作です。
設定について
主人公の子スズメは孤児で姉に育てられていて、アイヌの村に穀物を拾いに行きたいのですが、姉が許してくれません。
姉に育てられている孤児というのはユカㇻ(英雄の物語)でお約束の設定ですし、ウイマㇺ(和人の住む町へ交易に行くこと)に行きたがる若者を親が許してくれないというのはウウェペケㇾ(人間の物語)によくある設定です。これも一種のアイヌ文学のテクニックでしょう、スズメの世界を人間と等身大に置き換えて、違和感なくスズメの物語世界に聞き手を誘っています。
テーマ
この物語のテーマのひとつは、スズメたちが穀物を拾っていて村人たちに追い払われた時、アイヌの娘が言った次のセリフだろうと思います。(以下、川上まつ子さんの日本語語り原文のまま)。
「うちの中からきれいな娘出てきて、『スズメでも何でも生きていくために餌拾うのに働きに出てきているのに、こんな小さいスズメらがたくさん食べれるもんであるまいし、おまえらのこぼしてるやつ拾っただけでも余るだけ拾って食べたり持って帰れたりするのに、何でそんな意地の悪いことするんだ』って、その物搗いてる人たちに怒りつけながら、たくさんのヒエをとって、杵振り回したり足踏みしたりする女達から離れたとこに空けて、『スズメ、ここへきてたくさん食べたり拾って背負って帰ったりしなさい』って言ってくれた。」 |

静内地方(現在の新ひだか町)の織田ステノさんも同様に次のように語っています。「スズメが穀物を食べてしまっても、全て食べるわけではないからといって好きに食べさせていました。」(自然図鑑「スズメ」の項参照)
アイヌの動植物に対するやさしいまなざしを感じると同時に、「生きていくために働きに出てきているのに」というところに、川上まつ子さんの生きてきた道のりを重ね合わせて考えてしまいます。
挿入歌
この絵本では、途中にトンコリ伴奏の挿入歌が入っています。魔物を笑わせようとスズメが大活躍する山場で、オリジナルの物語では「歌を歌いながら跳ねたり踊ったりして笑わせようとした」というだけで、特定の歌が入っていたわけではありません。今回使用した挿入歌は樺太アイヌの伝承歌で、音楽担当の千葉伸彦さんによるもの(厳密には、千葉伸彦さんの歌をいつも聞いていた朗読担当今津朋子夫人の発案)。これが実にピッタリはまっていて、今津朋子さんのノリノリの歌、小笠原小夜さんのかわいらしい絵と相まってこの絵本の魅力のひとつになっています。
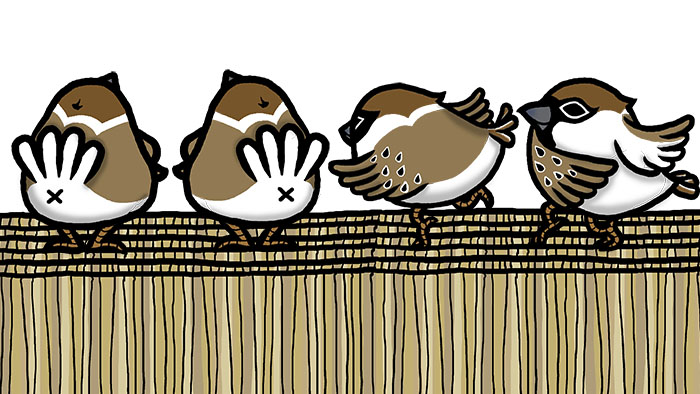
以下は千葉伸彦さん自身の解説です。
歌詞はいくつかの言い方があるようで、私もふだんはちょっと違った言い方をしたりしていますが、今回は公のものということで、『アイヌ伝統音楽』(日本放送協会、1965)から取りました。歌っている歌詞と意味は、伝統音楽から抜き出せば、以下のものです。 エトゥクマ カラ ウ ウ カラ
|
※この曲の詳細は、千葉伸彦「藤山ハルのトンコリ演奏法について(1)」「藤山ハルのトンコリ演奏の内容について」(『北海道東部に残る樺太アイヌ文化I』(常呂町樺太アイヌ文化保存会、1996)に詳しい。
ペウタンケ(危急の叫び)
物語の中で、美しい娘さんが死にかけた時、男たちは神へ祈り、女たちは「フォーイ、フォーイ」と、「災いを知らせる女の叫び声」をあげます。これは今で言えばサイレンのようなものです。川上まつ子さん自身はアイヌ語で「ペウタンケ」、日本語では「遠吠え」と呼んでいます。

これについて知里幸恵は次のように解説しています。
「マッリミㇺセ matrimimse(女の叫び声)……何か急変の場合またはウニウェンテuniwenteの場合、男はホコㇰセ hokokse(フオホホーイ)と太い声を出しますが、女はほそくホーイと叫びます。女の声は男の声よりも高く強くひびくので神々の耳にも先にはいると云います。それで急な変事が起こった時には、男でも女の様にほそい声を出して、二声三声叫びます。 |
(やすだ ますほ)
(次回は第二話「クモを戒めて妻にしたオコジョ」を紹介します。お楽しみに)
シンリッウレㇱパ(祖先の暮らし) 第1回
文・絵 北原次郎太(北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)
(1)
アイヌ民族が暮らしてきた土地は本州に比べて寒冷で、夏が短く冬が長いところです。伝承によれば、この世界はコタンカㇻカムイという神様が丹精込めて創った世界、言ってみれば美しい庭園のような場所です。そこはたいへんに風光明媚で、神界に暮らすカムイ達でさえ感銘を受けるほどです。アイヌモシㇼを訪れたカムイの話を聞き、他のカムイたちも一度は訪れてみたいと願うというのですから、まるでリゾート地のようですね。北海道よりも南に暮らしてきた人々からすれば過酷な荒地に見えるかもしれませんが、寒い土地だからこそ手に入る産物もあり、工夫ひとつで快適に暮らすことができる楽園なのです。
アイヌ民族は、この土地で、採集や狩猟、漁労と農耕を組み合わせた、複合的なライフスタイルを選びました。農耕や牧畜は、はじめに目標とするライフスタイルがあり、それに合わせて環境を変えていく暮らし方です。アイヌが選んだのは、農耕もある程度行いつつも、基本的にはそこにある物に応じた暮らしを組み立てるという方法でした。もっとも、採集の文化は、程度の違いこそあれ地球上の多くの民族にみられるものです。「米の文化」、「農耕民族」といわれる日本の暮らしにも、豊かな採集文化があります。それが、ムリのない暮らし方であり様々な環境に適応しやすいからこそ世界中に広がっているのでしょう。
葛野辰次郎というエカシ(長老)は「タシロ(山刀)とマキリ(ナイフ)だけあれば山の中で何日でも過ごせる」とおっしゃっていました。ほかに何も持たずとも、刃物と知識さえあれば、手早く家を建て、燃料を調達し、余裕を持ちながら思うままに動きまわることができるのです。もちろん食べる物もあります。アイヌ語では、自然の中から食糧を得ることを「カムイが作った食糧庫にはしごをかける」と表現します。山を良く知っていた先人達の目には、林野は食べ物に満ちており、庫から物を出す感覚でそれを得られると感じられていたのですね。山は、まさに庭であり畑でもある、そんな場所でした。

プ(食糧庫)の前で臼と杵で穀物をつく女性たち。右では女性が箕(み)を振るう(木下清蔵遺作写真より)
(2)農耕
それでは、季節ごとにアイヌモシㇼでの暮らしを見てみましょう。アイヌモシㇼにもパイカㇻ「春」、サㇰ「夏」、チュㇰ「秋」、マタ「冬」の四季があり、また大まかにサㇰパ「夏の年」、マタパ「冬の年」の2つに分けてとらえることもあります。樺太のアイヌ民族は、夏の年の間は海浜近くに住み、冬の年は山すそに移り住むという季節移動をしていました。北海道では年間を通して定住しますが、サㇰコタン「夏の村」やリヤコタン「年越しの村」などの地名から、かつては季節移動の習慣があったことが伺えます。
月の満ち欠けによって、1年を12ヶ月に分けていましたが、他にも季節を知らせる自然からのメッセージがあります。例えば鳥の声がその一つです。カッコーはアイヌ文化においては美声の代名詞となっている鳥であり、種まきの季節を知らせる鳥でもあります。毎年カッコーの鳴き声が響くようになると、人々は種まきの季節が来たことを知るのでした。
アイヌモシㇼでは擦文文化(7〜12世紀)の頃から農耕が行われていたことが知られており、ヒエ、キビ、アワ、ソバ、カブ、後にはカボチャやジャガイモなどが栽培されました。農耕の規模はそれほど大きくありませんが、文化的には大変重要なものです。たとえば、穀物から作られる団子と酒は、神事の際の最も重要な捧げ物となります。
また、農機具は道具の神の中でも力の強い神とされ、鎌は魔物や苦しみを断ち切る力があり、杵は地震をしずめるのに用い、臼は大風から家を守り、また出産を助ける神だとされています。今ではあまりなじみのない道具かもしれませんが、殻と実を分離するのに用いるミという農具があり、これに赤ん坊を乗せて揺すると、丈夫な子になるといいます。(臼、杵、箕は上の「木下写真」参照)
ジャガイモは、ヨーロッパからジャカルタを経由して本州に運ばれ、アイヌモシㇼには18世紀の間にもたらされたと考えられています。初めてジャガイモがもたらされた時の驚きと喜びを表現した歌が伝わっていますが、それほど愛されたジャガイモは、わずか200年ほどの間にアイヌの食生活の中に深く浸透していきました。また、ペネイモ、ポッチェイモなどと呼ばれる保存食があります。これは、冬季の冷え込みを利用し、凍結と解凍を繰り返すことで水分を抜く保存法ですが、面白いことにジャガイモの原産地アンデスにもよく似た保存食があります。ジャガイモが、温暖な南方を回って伝わったことを考えると、おそらくこの保存法は北海道に渡ってから考案されたのでしょう。(北原次郎太)
 油で焼いたペネイモ(アイヌ民族博物館カフェリㇺセ提供)
油で焼いたペネイモ(アイヌ民族博物館カフェリㇺセ提供)
(次回のシンリッウレㇱパは「採集」「漁労」です。ご期待下さい)
図鑑の小窓1「アカゲラとヤマゲラ」
冬は葉が枯れ落ち、キツツキなどの鳥たちを観察するのには絶好の季節です。アカゲラもヤマゲラも留鳥なので一年中その姿を見るチャンスがありますが、普段から人前に比較的よく姿を見せるアカゲラに対し、ヤマゲラはあまり姿を見せません。しかし冬になると山から人里近くにおりて来るので、姿を見る機会がより多く訪れるのです。
アカゲラ(エソㇰソキ/ニトㇰトキ等) (2012/11/24 苫小牧 安田千夏撮影)
ヤマゲラ(シルㇱチㇼ) (2013/6/28 白老 安田千夏撮影)
アイヌ民族博物館のデジタル絵本「アカゲラになった女の子」は、こんなお話です。「あるところにおばあさんとふたりきりで暮らす女の子がいました。でもその女の子は家の仕事をするのが嫌になり、『きれいな着物を着せてくれなければ水汲みに行かない』と言いました。そこできれいな着物を着せてもらうと、今度は水汲みに行っても水鏡に映る自分の姿に見とれて遊んでばかり。そのうちにおばあさんは年老いて水を飲むこともできずに死んでしまいました。神様はそんな女の子に罰を与え、アカゲラにして水を飲むことをできなくしてしまいましたとさ」。

沙流地方の川上まつ子さんも、若い頃「アカゲラはきれいな着物を着ていてうらやましいなあ」と思ったと語っておられ、このお話とはきれいな着物を着ているという印象が共通しています。なるほどアカゲラは黒と白のシックな色あいをベースに、さし色に赤をあしらったなかなかおしゃれな着物を着ています(写真1)。ところが静内地方の葛野辰次郎さんは、アカゲラについて「この鳥を鉄砲で撃つと、一生あのようなボロボロの着物を着なくてはならなくなる」とおっしゃっています。そう言われてみると、今度は穴が開いたぼろをまとっているように見えて来ますね。アイヌ文化では人によって色々な想像力を働かせながら鳥を観察していたことがわかります。
さて静内地方の伝承者である織田ステノさんは、ヤマゲラについてアカゲラとよく似た話をされています。「ヤマゲラはもともと人間の子供だったのですが、祖母の言うことを聞かず水汲みを怠けたために、罰を受けてヤマゲラにされてしまいました。そしてさらに鳥になってからも水場に降りて水を飲むことを許されず、葉にたまったつゆを飲み、虫をつついて食べることしかできないのです。もし万が一水場に降りて水を飲んでいるところを見かけたらすぐに神様にそのことを告げ口しなければ、それを見た人間の方に災いが及ぶのです」。
昨年の夏のこと、私が白老の森を歩いていると突然水辺から飛び立った鳥がいました。見るとそれはまぎれもなくヤマゲラで、織田さんのお話にある通りこっそりと水辺で水を飲んでいたのでした。そしてその後ヤマゲラは飛び去ることはなく、近くの木にとまってしきりとこちらの様子をうかがっていました(写真2)。まるで私が神様へ告げ口をしないかどうかを見張っているかのようで微笑ましかったものです。うろたえた様子がかわいそうだったので告げ口はやめておきましたが、幸いなことにその後私が災難に見舞われるということもありませんでした。
博物館のデータを見る限りでは、最大のキツツキの仲間であるクマゲラについては罰を受けるという類の話は採録されていませんし、小型のコゲラやキバシリについても然りです。ヤマゲラとアカゲラが特にこうした話の主人公となっている理由は何でしょうか。そんなことを考えながら鳥との出会いを求めて厳冬期の森を歩くのも楽しいものです。(安田千夏)
「月刊シロㇿ」とは
「月刊シロㇿ」はアイヌと自然をテーマにしたWEB雑誌です。シロㇿ sirorとはアイヌ語で「自然」という意味。主要なアイヌ語辞書にも出て来ない言葉ですが、葛野辰次郎というエカシ(長老)が自ら出版した『キムスポ』という本には繰り返し(65回)登場し、エカシ自身が「自然」「大自然」と訳をつけています。シロㇿというアイヌ語ともども誌名を覚えていただき、末長くご愛読いただければ幸いです。

アイヌと自然、カムイたちが主役だった時代、この北の大地には私たちの知らない豊かな暮らしがありました。
「その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児の様に、美しい大自然に抱擁されてのんびりと楽しく生活していた彼等は真に自然の寵児(ちょうじ)、なんという幸福な人だちであったでしょう。
冬の陸には林野をおおう深雪を蹴って、天地を凍らす寒気を物ともせず山又山をふみ越えて熊を狩り、夏の海には涼風泳ぐみどりの波、白い鴎(カモメ)の歌を友に木の葉の様な小舟を浮かべてひねもす魚を漁り、花咲く春は軟らかな陽の光を浴びて、永久に囀(さえ)ずる小鳥と共に歌い暮して蕗(フキ)とり蓬(ヨモギ)摘み、紅葉の秋は野分に穂揃うすすきをわけて、宵まで鮭とる篝(かがり)も消え、谷間に友呼ぶ鹿の音を外に、円かな月に夢を結ぶ。嗚呼(ああ)なんという楽しい生活でしょう。……」(知里幸恵『アイヌ神謡集』序より)

1922年、この美しい文章を書いた18歳のアイヌ女性・知里幸恵は、そのまなざしを過去から未来へ転じ、アイヌ神謡を後世に残す意志をこう続けました。
「けれど……愛する私たちの先祖が起伏す日頃互いに意を通ずる為に用いた多くの言語、言い古し、残し伝えた多くの美しい言葉、それらのものもみんな果敢なく、滅びゆく弱きものと共に消失せてしまうのでしょうか。おおそれはあまりにいたましい名残惜しい事で御座います。」
アイヌ民族博物館もまた設立以来、同じ志をもって各地のエカシ(長老)やフチ(おばあさん)の話を録音し、後世に残すべく努めてきました。話を録音させてくれたエカシやフチたちもまた、同じ気持ちで私たちに協力してくれたに違いありません。「アイヌと自然デジタル図鑑」では、古老たちが残した録音をもとに、アイヌと自然に関する口述や物語をまとめ、データベース化しました。またアイヌと自然を語る上で欠かせない労作、知里幸恵の弟にあたる知里真志保の『分類アイヌ語辞典 植物編・動物編』も併せて収録しました。
古老たちの思いに比して不十分な点の多い創刊となりますが、今後この図鑑が皆さんに愛され、号を重ねるなかで、北の大地に生きる先住民族アイヌと自然に理解を深め、また未来を担う若きアイヌ民族のアイヌ文化継承活動の一助となることを願います。
本文ここまで
ここからフッターメニュー