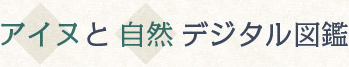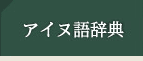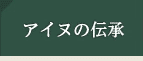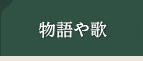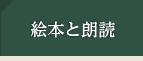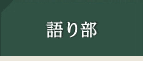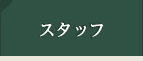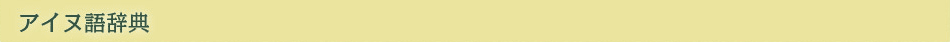植物編 §139 シナノキ Tilia japonica Simk.
アイヌは、この樹の内皮で縄を作った。天塩では、山のアイヌがその縄を多量に作って浜へ物々交換に来たという。また、この内皮をさらして繊維をとり、狩りや漁に行く時の脚絆などに織った。そこで、この内皮、またはその繊維にまず名がつく。
(1)nipes ニペㇱ [ni(木)pes(もぎとった裂皮)] 内皮、またはそれから取った繊維 ⦅長万部、虻田、有珠、室蘭、幌別、穂別、千歳、沙流、名寄⦆
注1.――pesは、mes-ke(もげる)mes-u(もぐ)などの語根mesや、per-ke(割れる)per-e(割る)などの語根per、pet-ke(裂ける)pet-u(裂く)などの語根petなどと関係があり、ni-pesは「木からもぎ取った裂片」を意味したらしい。
(2)si-nipes シ・ニペㇱ [本当の・ニペㇱ] 内皮、またはそれから取った繊維 ⦅穂別⦆
注2.――オオバボダイジュの繊維を「ヤイ・ニペㇱ」(ただの・ニペㇱ)というのに対して、シナノキのそれを、「シ・ニペㇱ」(本当の・ニペㇱ)というのである。
注3.――シナノキの内皮から取った繊維を灰汁で煮ると淡紅色を呈する。河野常吉氏の調査によれば沙流郡平取付近のアイヌはそれを『チポッペニペㇱ』と言ったとある(河野広道、アイヌの織物染色法、p.70)。「チぽㇷ゚テ・ニペㇱ」ci-popte-nipes(我ら・煮立てた・シナ皮の繊維)の誤りである。
(3)kuperkep クペㇽケㇷ゚ [<ko-perkep, ko(共に)perke(裂ける)p(もの)] 内皮、またはそれから取った繊維 ⦅美幌、屈斜路、足寄⦆
(4)kukerkep クケㇽケㇷ゚ [<ku-perke-p] 内皮、またはそれから取った繊維 ⦅荻伏、様似⦆
(5)on-kukerkep オン・クケㇽケㇷ゚ [on(鮮度の落ちた、なれた)kukerkep(シナノキの繊維)] 水の中につけておいてべとべとにやわらかくなった繊維をいう ⦅様似⦆
注4.――樹皮から繊維を取る時は、表皮を削り去って、内皮を水につけておき、ねろねろを洗い去って乾燥して使うのである。
(6)nipes-ni ニペㇱニ [ニペシの取れる木] 茎 ⦅長万部、虻田、有珠、室蘭、幌別、穂別、千歳、沙流、名寄⦆
(7)kuperkep-ni クペㇽケㇷ゚ニ [クペㇽケㇷ゚の取れる木] 茎 ⦅美幌、屈斜路、足寄⦆
(8)kukerkep-ni クケㇽケㇷ゚ニ [クケㇽケㇷ゚の取れる木] 茎 ⦅荻伏、様似⦆⦅A十勝⦆
(9)sinipes-ni シニペㇱニ [本当のニペㇱの取れる木] 茎 ⦅穂別⦆
注5.――オオバボダイジュを「ヤイニペㇱニ」(ただのニペㇱの取れる木)というのに対する。
(参考)沖へ出ると「シㇼカㇷ゚」sirkapメカジキがあの「ハイ」hay(上あごが伸びて剣のようになったもの)を磯舟の底に突き通すことがある。それで、沖へ乗り出す時は、それを切断するため山刀を研いで持って行くことを忘れない。また、メカジキの剣を突き刺されても割れないように、舟底は必ずシナノキで作った(長万部)。