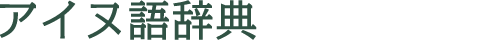植物編 §001 エゾヨモギ Artemisia vulgaris L. var. yezoana kudo
(1)noya ノヤ [“もみ草”の義] 葉をいう ⦅北海道、樺太⦆
注1.――語源については、参考1(p.2)に詳説する。→補注(1)
(2)yayan-noya ヤヤンノヤ [yayan(普通の)noya(もみ草)] 葉 ⦅A有珠⦆
注2.――学名と等しく“普通にあるヨモギ(もみ草)”の義。
(3)matne-noya マッネノヤ [mat(女)ne(である)noya(もみ草)] 葉 ⦅幌別⦆、⦅A有珠⦆
注3.――pinne-noya“雄の・もみ草”に対する。→§4、(1)、参照。
(4)nupun-noya ヌプンノヤ [<nupur(霊験ある)noya(もみ草)] 葉 ⦅A石狩⦆
注4.――霊験については“参考1”参照。
(5)kamarusa カマルサ [kam(肉)o(入る)rusa(すだれ)] 葉 ⦅大泊⦆
注5.――ヨモギの長い茎ですだれを編み肉をのせて乾かす土俗が各地にあり、それに基づいてこの名が生じたらしく、もとは茎をさす名称だったと思われる。→補注(2)。
(6)『チクルペ』 ⦅蝦夷方言藻汐草⦆
注6.――おそらくcikurpe[ci(我ら)kur(当てる)pe(もの)]で、葉をもんで傷口に当てて血を止めた土俗に基づいた名であろう。→§9、(3)、ikur、参照。
――以上いずれも葉を表す名称である。茎を表すにはそれにikkew(-e)「背骨」あるいはnit(c-i)[棒]をつけて次のように言う。
(7)noya-ikkew ノヤイッケウ [もみ草(の)・背骨] 茎 ⦅幌別⦆
(8)noya ikkewe(-he) ノヤイッケウェ(ヘ) [もみ草・の背骨] 茎 ⦅幌別⦆
(9)noya-nit ノヤニッ [もみ草(の)・棒] 茎 ⦅幌別⦆
(10)noya-nici(-hi) ノヤニチ(ヒ) [もみ草・の棒] 茎 ⦅幌別⦆
――根を表すにはsinrit(c-i)[根、<sir(大地)rit(筋)]あるいはcinkew(-he)[根、<cin(脚)kew(骨)]を付ける。
(11)noya-sinrit ノヤシンリッ [もみ草・根] 根 ⦅幌別⦆
(12)noya sinrici(-hi) ノヤシンリチ(ヒ) [もみ草・の根] 根 ⦅幌別⦆
(13)kamarusa-cinkew カマルサチンケウ [ヨモギ・根] 根 ⦅大泊⦆
(14)kamarusa cinkewhe カマルサチンケウヘ [ヨモギ・の根] 根 ⦅大泊⦆
(参考1)ヨモギの類は、いずれも食用に供した。葉をゆがいて乾しておき、粟などに搗きまぜて、「ノヤシト」noya-sito“ヨモギ・だんご”を作った。また取りたての若葉を刻んでおき、粥が煮えたらその上にふりかけてしばらくしてから鍋をあげると、粥にヨモギの香が移って、たいへん香ばしい粥ができあがる。それを「ノヤサヨ」noya-sayo“ヨモギ・かゆ”と言い、嗜好の上からばかりでなく、それを食べると回虫が湧かぬと言って、ヨモギの萌え出る頃になると、どこの家でも必ず作って食べたものである。
葉はまた煎じて咳どめ・虫くだし等にも飲用した。青葉をもんで怪我した際の傷口に当てて出血を止め、虫歯の痛む際はそれを塩もみして絞り汁を痛む穴に垂らし込んだ。わきがの臭みをとるのにもこの葉をもんで拭い、あぶら手を清めるのにもこの葉を両手でもんでそれから洗い落とした。枯葉をもんでもぐさにもした(幌別)。
以上の点から見て、noyaの語源は、おそらく「ノヤノヤ」noya-noya“こすりにこする” “もみにもむ”から来たものとしていいであろう。
ヨモギの茎葉の青いのは蚊やりに焚いたし、枯れたのは焚きつけにもした。これを焚きつけにすれば、火の神が喜ぶ、という信仰があった(幌別)。
この点に関して、アイヌ神話の中でヨモギがアカダモの木と共に火の創造に関連して述べられているのは、著しく私どもの注意を引く。(火の創造に関する神話については、アカダモの所で詳しく説いた。→§298参照)。
「コタンカㇽカムイ」(この神の正体については§144“参考3”に説いた)が人間の国土を創造した際、草木の中で最初に生じたのは、国土の西方においてはドロノキとワラビであり、東方ではハルニレとヨモギであった。「コタンカㇽカムイ」は人間に火を授けようとして、先ずドロノキで火きり棒と火きり台とを作り、もみにもんだが火は出なかった。そこで次にハルニレで試みたら、初めて火が生じた(沙流)。
この神話によって、私どもは、第一に、ドロノキがなぜ「ヤイニ」yay-ni“ただの・木”とよばれるか、第二に、ハルニレがなぜ「チキサニ」ci-kisa-ni“我らが・もむ・木”とよばれるか、の理由を知ることができるばかりでなく、第三に、ヨモギもまた、もんでほくちなどに用いられたらしいこと、およびヨモギを意味するnoyaという名称が、「もむ」という原義において、ハルニレのci-kisa-niと連想されているらしいこと、等を知り得るのである。
ヨモギの葉をもむと、一種特有の臭気を発する。この臭気のゆえに、アイヌはヨモギに除魔力を認め、ひろく呪術や治療に用いる。これがヨモギに「カムイノヤ」kamuy-noya“神なる・ヨモギ”あるいは「ヌプンノヤ」nupun-noya“霊力ある・ヨモギ”の名の生じているゆえんである。
千歳では、風邪の際、この茎葉を鍋に入れて煎じ、湯気が盛んに立ちのぼるようになったら、頭から着物をかぶって鍋の上に伏し、その湯気を受けて汗を出す療法があった(こういう療法をyaysamawkareと言い、北の方では盛んに行われる。索引によって参照されたし)。またその煎汁を飲んだ(関場不二彦、あいぬ医事談、p.59)。
ヨモギの茎葉を束ねて、悪夢を見た時などそれで身体を祓い清めるための「タクサ」takusa“手草”にする。そういう手草で体を祓い清めることをka(-si、-si-ke)-kikと言う。[ka(上)、kasi(その上)、kasike(その上の所)、kik(打つ)]。例えば自分で自分の体を祓い清めることをyay-ka-kik(自分・の上を・打つ)と言い、誰かの体を祓い清めることをkasi-kik(彼の上を・打つ)kasike-kik(彼の上の所を・打つ)などというのである。epiruともいう。索引によって参照されたし。マラリアのあった時も、近所の者が集まって来て、この手草で病人の背中を叩き、病魔を追い出そうと努力する(幌別、沙流、屈斜路)。あるコタンでは、癲癇(てんかん)様の病気にかかった少年を治すのに、その少年を山中のカシワの木の下に連れて行き、そのカシワの木のように丈夫になるようにと祈った後、持って行った鎌で少年の着ていた衣服をずたずたに裂き、その裂け目から病魔を叩き出すかのようにヨモギの手草で全身を叩き祓い、あらかじめ用意してあった新しい着物に着替えさせてから家へ連れて帰ったという(バチラー、アイヌ人とその説話)。
重病人のある時、ヨモギで人形の形を作って着物を着せ、病人の病気を全部それに移したことにして戸外に捨てる所もある(D屈斜路)。
疱瘡(ほうそう)その他の伝染病が村へ入らないように、村境や川口に、ヨモギで草人形を作って立てることもある(久保寺逸彦・知里真志保、アイヌの疱瘡神パコロカムイに就いて、人類学雑誌、第55巻第3、4号)。ヨモギを入口にさして病魔が家の中へ入らないようにする(D屈斜路)。何か嫌なもの、例えばキアゲハ蝶などを見るとヨモギの鞭で六回叩く(D屈斜路)。
ヘビが穴の中へ逃げ込んだ際は、ヨモギの串を作って穴の口へ立て、「なぜお前は姿を見せたのだ? それはよくない所業だ。ヨモギの勇士をここに立たせておくから、お前はもう帰れないよ」という意味の呪文を唱える(幌別)。蛇を殺した時は必ずヨモギの串を作って頭を刺し止めておく。さもないと生き返って祟ると信じている(幌別)。
この信仰が説話の中にも反映して、勇者が悪神を退治するのにわざわざヨモギの矢をもってする話が多い。オキキリムイの射たヨモギの矢に当たって死んだ暴風雪の魔が、「俺の頭の頂から足の先まで、樺の皮が燃えるように痛む。たかが人間の射た小さな矢がこんなに俺を苦しめようとは思わなかった」と告白している(知里幸恵、アイヌ神謡集、p.46)。→補注(3)。
このように、この植物は、アイヌの信仰上特別の意義を有し、アイヌはそれに特別の霊能(除魔力)を認めているので、それを食用にするのは、単に口腹の欲を満足させるだけのものではなく、それを体内に摂取することによって病魔を遠ざけ、心身を健康に幸福に保ち得るという信仰に基づくものであることがわかる。だからヨモギの若葉を摘みに春の野に出ることはアイヌ婦人の重要な年中行事の一つになっている。各地にヨモギに関する地名があり、例えば、
「ノヤ」noya[ヨモギ]――胆振国有珠郡(C、p.186)、日高国静内郡(大日本地名辞書、六巻、p.263)
「ノヤウシ」noya-us-i[ヨモギ・群生している・所]――十勝国中川郡(C、p.305)
「ノヤサルシ」noya-sar-us-i[ヨモギ・原・ある・所]――石狩国夕張郡(C、p.70)
「ノヤサロペッ」noya-sar-o-pet[ヨモギ・原・にある・川]――胆振国勇払郡(C、p.214)
などが見出されるのも、一つにはそういう理由によるのである。
なお、ヨモギの長い茎を取って「ノヤルサ」noya-rusa“ヨモギすだれ”を編み、小魚や食糧を乾すのに用いた(幌別)。これは各地でする。樺太の大泊(クスンコタン)地方でヨモギを「カマルサ」(肉をのせるすだれ)と言っているのは、それから生まれた名称と思われる。
(参考2) 前記ヨモギ人形というのは、ヨモギの茎を束ねて作った草人形で、非常に恐ろしい神とされ、人間の手に負えぬような悪神や魔物を退治するためにだけ作られ、やたらに作ることは禁忌とされている。
その作り方は、地方によって多少ずつ違っているようであるが、日高の沙流ではヨモギの茎を束ねて頭部・胴体・及び四肢を作る。ただし、下肢にはヤナギの棒をさして心にする。手には「ノヤオㇷ゚」noya-op“ヨモギ・槍”を持たせ、腰には「ノヤエムㇱ」noya-emus“ヨモギ・太刀”を差させる。なお、頭部と腰部を「チノイェイナウキケ」ci-noye-inaw-kike“我らが・撚った・幣の・削り花”で縛り、手にも削り花を垂らしている。頭部を縛るのは“kamuy sapa muye”「神の頭を束ねた」姿で、腰部を縛るのは“kamuy a-kut-kore”「神に帯をしめさせた」姿である。これを作る際、頭・胴体・両手・両足の六部に消し炭でsampe“心臓”を入れる。この神は特に丁重に取り扱い、必ず「イナウソ」inaw-so“幣・座”と称する花ござを作って、その上に安置する。→補注(4)。
ヨモギ人形を最初に作ったのは、アイヌの始祖「アイヌラックル」だと言われる。この「アイヌラックル」なるものは、実は古代社会における呪師だった(§144、参考3、参照)。従って、ヨモギ人形などもその呪術において盛んに用いられたであろうことは、当然考えられるのである。その名称のimos-kamuyの語源なども、従来は“目を覚ました神”と解されていたけれども、それは単なる思いつきにすぎず、語学上からも難点があるのであって、本当は、imos-kamuy<imu-us-kamuy“イム(呪術)に入った神”の意ではなかったかと思われる。
ヨモギ人形には、次の様に多くの名称がある。
(1) imos-kamuy<imu-us-kamuy“イム・に入った・神”。イムという語が、北部地方の詞曲の中では、tusuと並んで、呪術の意味に用いられることがある。それがあるいは原義だったかもしれない。イムについては§144、参考2、参照。
(2)「ノヤイモㇱカムイ」noya-imos-kamuy“ヨモギの呪術に入った神”
(3)「チシナㇷ゚カムイ」ci-sina-p kamuy“我ら・結んだ・者(である)・神”
(4)「ムンチシナㇷ゚カムイ」mun ci-sina-p kamuy“草を・我ら・結んだ・者(である)・神”
(5)「アイヌテケカㇽカムイ」aynu-tek-e-kar-kamuy“人間の・手・で・作った・神”
(6)「チテケカㇽクㇽ」ci-tek-e-kar-kur“我らの・手・で・作った・神”
(7)「アイヌモンカエヌプㇽカムイ」aynu-mon-ka-e-nupur-kamuy“人間の・手・の上・で・呪力をもった・神” “人間の手によって呪力を持った神”
(8)「キナストゥイナウカムイ」kina-sutuinaw-kamuy“草の・棒幣・神”。棒幣については§206、注1、2、3、参照。
(9)「レワレワックㇽ」rewarewak-kur“たわみたわみする・神”等。→補注(5)。
次に掲げるのは、日高の沙流に伝えられていた神謡で、“apto sasun sasun”「雨の音さらさら」という折り返しをもって歌われるものである。
ある日、つれづれなるままに、わが里川であるシシリムカの奥にある神山、神山の上に横たわっている倒れ木、その倒れ木の上に腰をおろして、いろいろな歌を、咽喉の奥をたくみにしぼって歌っていると、歌声の片枝が大空さしてのぼって行く。その声朗々として響きわたり、歌声の片枝が沖合はるかに流れて行く。その声朗々として響きわたる。歌声の流れて行く先々に、光明神たち魔神たち、舞い踊る音とどろきわたる。そうしていると、気もはればれとしてくるのであった。
その時、俺の背後に何の音であろうか、ばたりばたりという音、どしんどしんという音がするので、何の音かと不思議に思って、肩越しに振り返ってみると、幣場の神が蛇体をあらわして、尾を振り上げ振り上げ大地を打って拍子をとっていっているのであったが、それが二つの言葉のふし三つの言葉のふしになって、俺の耳にこう響いてくるのであった。
「小オキクルミよ、そんなにお前は目が見えないのか? お前の里川であるシシリムカの川口に神の舟が上って来て、お前の村お前の国を荒そうとしているところだよ。そんなにお前は目が見えないのか?」
そういうことが、二つの言葉のふし三つの言葉のふしとなって、俺の耳に響いて来た。そこで、わが里川の川口の方を振り返って見ると、笹の葉の舟のようなものが、海草のより上がるようにおびただしくわが里川の川口に上っている。とっさの間に、どうしたらよかろうかと思案をめぐらして、ヨモギの茎を結んで、草人形の神を作り、それに二つの言葉三つの言葉を言い聞かせた。すると、あたりにさっと音がして、激しい神風が吹き起こった。その神風に乗って飛び上がり、わが里川の川口に飛び去ったかと思うと、そのとたんに激しい神戦がまき起こったようである。草人形の神ひとりを神の戦、戦の庭にひとりやるのは心もとなく思ったので、棒幣の神を手早く作り、それに二つの言葉三つの言葉を言い聞かせた。するとあたりにさっと音して神風が吹き起った。その神風の上に乗って飛んで行き、わが里川の川口に消え去った。それからずうっと、神々の戦闘が激しく戦われているらしく思われた。沖の広庭、広庭の上に、この戦闘が逆に押し戻されて行くらしく、その音がいんいんと響いている。そこまで聞き届けて、俺は自分の家に戻り、いつもと同じく暮らしていると、ある日、はるか沖の方から、神のやって来る音がいんいんと鳴り響いて、波打ち際まで来ると、はたと絶えた。すると、またもやはるか沖の方から神の来る音がいんいんごうごうと鳴り響いた。その音の激しさから推して、いずれも皆非常に重い神々であるらしく思われた。浜手の草原と山手の草原のまん中まで上って来ると、音の先がはたと絶えた。
その時はじめてわが手で作った神々が戻って来たのだなと気づいたので、二抱えの木幣三抱えの幣を削って浜へ持って出た。見ると最初にわが手で造った神、草人形の神は、ただ背骨だけただ腰骨だけが助かった無惨な姿で、波打ち際まで帰って来てそこで倒れたのであった。最後に頼んだ神、棒幣の神は、浜側の草原と山側の草原との境まで上って来て、そこで倒れたのであった。かわいそうだなという気持ち、気の毒だったなという気持ちを俺は持った。
そこで草人形の神は、浜の入江、入江の東口に祭って、そこを守らせた。また棒幣の神は、浜手の草原に祭ってそこを守らせた。それゆえ、人間の孫たちが、浜の入江、入江のほとりに出て来てお祭りをすると、その守り神となって、入江の中で遭難しても、沖で遭難しても、浜の草原を、守っている神が、乗っている航空船の引綱と鉤を使って、人間の孫を船首に引きあげてくれるから、無事に本国へ帰ることが出来るのである。→補注(6)。