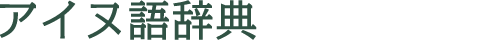植物編 §144 キツリフネ Impatiens Noli-tangere L.
(1)imu-kina イムキナ [imu(イムの発作をする)kina(草)] 茎葉 ⦅白浦、白主⦆
注1.――イムは、何かに驚いた拍子に反射的に行動することをいう(詳しくは“参考2”に説く)。この草の熟した果実は、それにちょっとでも触れると、とたんに果皮がくるりとよじれて種子を弾き飛ばす。そのさま、すこぶるイムに似ているので、“イムする草”と名づけたのである。
(2)hopenu-kina ホペヌキナ [hopenu(びっくりして飛び上がる)kina(草)] 茎葉 ⦅白浦⦆
注2.――hopenuは、ho(尻を)penu(あげる)ということで、びっくりして飛び上がることである。この草の熟した果実に触れると、とたんにくるりとよじれるさまに名づけたのである。“びっくり草”。
(3)pahtaki-kina パㇵタキキナ [pahtaki(バッタ)kina(草)] 茎葉 ⦅真岡⦆
注3.――pahta-ki、pahta(<pattaバッタ)-ki(昆虫)。果実がはじけるのにバッタの跳ぶさまを連想したのである。
(4)opke-mun オㇷ゚ケムン [opke(放屁する)mun(草)] 茎葉 ⦅幌別⦆
(5)teknuyep テㇰヌイェㇷ゚ [tek(手)nuye(<nuyeもむ)p(者)] 茎葉 ⦅様似⦆
注4.――果皮が裂けてよじれるのに、両手をもんで礼拝するさまを連想したのである。意訳すれば“おじぎ草”である。
(6)“nikiniki-kina” 『ニキニキキナ』 ⦅B⦆
注5.――辞書には例によって使用地を明記していないが、植物誌(E、p.86)に、『ニキニキキナ』(樺太アイヌ名)、とある。たぶん、「ニキニキ・キナ」nikiniki-kina(ni-ki-ni-ki-ki-na)[nikiniki(折りたたむ)kina(草)]で、茎葉をさしたものである。果皮が裂けてよじれるさまに名づけたのであろう。
(7)kakkok-mun カッコㇰムン [kakkok(カッコウどり)mun(草)] 茎葉 ⦅美幌、屈斜路、足寄、本別⦆
注6.――“カッコウ草”という理由は“参考1”で説く。
注7.――コタンの子供たちは、この花を人さし指にはめてピョコピョコ動かしながら、“カッコウ! カッコウ”とカッコウ鳥のまねをして遊んだ。それで、この花の名称をkakkok-humとして“カッコウの鳴き声”だと解している人もあるらしい。コタン生物記(D、p.66)には『カッコフン』とある。“カッコウ鳥の鳴き声”ならkakkok-hawでなければならぬ。kakkok-humは“カッコウの音”の義である。
(8)kakkok-kina カッコㇰキナ [“カッコウ・草”] 茎葉 ⦅名寄⦆
(9)kakkok-kamtaci カッコㇰカㇺタチ [kakkok(カッコウ)kamtaci(麹)] 花中にある白い玉(蜜腺) ⦅足寄、本別⦆
(10)“kakko-pus” 『カッコプシ』 ⦅B⦆
注8.――正しくは「カッコㇰプㇱ」kakkok-pus(kak-kok-pus)[“カッコウ鳥の幣”]で、花をさすのであろう。pusは穂の意味であるが、北海道の北東部では山中で神に祈る時に捧げる幣の意味にも用いる(樺太でも幣をepusiと称する)。アイヌは神に祈る時は必ず酒を捧げて祈る。しかるに山狩りなどに出た際は、酒を持って行くわけにはいかないので、その代わりに少量の穀物(米かヒエかアワ)と麹とを携えて行き、神に祈る際はその穀物と麹とを少量包んで木幣の先に吊るし、それを立てて神に祈る。つまり酒の代わりに酒の材料を上げますからはなはだ勝手ですがそちらの方で酒を造ってお上がり下さいという次第である。その幣の先に吊るす酒の材料をpus-kusuri(幣・薬)と称する。この花をkakkok-pus“カッコウの幣”というのは、その花の中に前記のごとく“カッコウの麹”があるので、そう名づけたのであろう。
(参考1)この花を子供らは人さし指の先にはめてぴょこぴょこ動かしながら、
kakkok ! kakkok ! (かっこう! かっこう!)
とカッコウ鳥の真似をして遊んだ(屈斜路)。また、花を裂いて中の白い玉を出し、それを「カッコウの麹(こうじ)」(kakkok-kamtaci)だと言って食べた(足寄、本別)。(7)以下の名称は、それにもとづいている。この植物は、その蒴の熟したものに触れると、たちまち果皮が弾けて種子を飛ばす。(3)(4)(5)(6)の名称は、それにもとづいている。赤児が生後1年以上も経つのになお歩かぬ時は、この植物の茎葉で体をさすり、また着衣の間にもそれを入れる。この果皮のはじけるように元気になれ、という呪法であろう(白浦)。膝の関節(「クイサマウシ」kuysamausi)がふくらみ筋が伸びぬ病気(「ポネウシチコイキ」pone-usi-cikoyki)に、この葉をもんでつける。生葉のない季節には、あらかじめ干し貯えてあったものを出して来て布に包み、あるいは袋に入れて患部に巻いておく(真岡)。
(参考2)イムには適当な訳語がないので、今では原語がそのまま一般に用いられている。そこでその意義について、簡単な説明を加えておこうと思う。
イムの語源は今の所まだよく分からない。ギリヤク語でもやはりそう言っている。語源はともかく、その意義には二つの場合がある。
一般に学者たちがイムと言っているのは、アイヌ人の間に往々認められる、ある特定の刺激に対する一種のヒステリー反応であり、何かに驚いた拍子に発作的に行動する特殊な病的症状をさすようである。その病的症状に二種あり、一つは人が右と言えば左、左と言えば右というぐあいに、全然外来の刺激に従おうとせず、理由なく反抗する風を示す能動的な拒絶症、いわゆる「命令的拒絶症」(Befehlsnegativismus)であり、もう一つはいわゆる「反響症状」(Echosymptome)で、それには相手の言語を反射的にそのまま繰り返す「反響言語」(Echolalie)と、相手の動作をそのまま真似る「反響動作」(Echopraxie)とがある。樺太のイムには、この後者が支配的であった。例えば、初めて氷上でアザラシを射当てて喜悦のあまり突然イムを起こして、逃げまわるアザラシの真似をした症例があり、また飛行機の飛ぶのを見て突然イムを起こして無意識にその真似をやっていた症例もある。
興味ある例としては、ある特定の言葉が暗示的刺激となって、特定の形式でイムを起こすように習慣化したものがある。樺太の東海岸の諸所で半生を漁夫として送った男、漁場でニシン粕などの入った俵を担ぎ上げるのに「ヤンサノ」という掛け声で担ぎ上げ、それを地上に「コリャサッ」と投げ下ろすのが習慣であった。この男のイムは、戸外にある時でも屋内に座っている時でも、誰かがそばで「ヤンサノ」と叫ぶと俄然イムを起こして、傍らにあるものは、物だろうと人だろうと一切おかまいなく担ぎ上げて「コリャサッ」と投げ出すのであった。
イム症状を誘発する刺激は必ずしも正常な知覚に限らぬ。幻覚によってもイムを起こす。先年、さるアイヌが個性幻覚というか、寝ぼけの夢から人殺しの凶行に及んだことがあった。こうなるとイムも社会的な脅威となる。
しかしながら、イムにはこうした病的症状の意味の他に、もっと一般的に軽い意味で、驚いた拍子に飛び上がるとか、あらぬ文句を口走るとか、またその口走った文句とかをもイムというのである。その口走る文句は個人個人で一定していて、目前の事象とは何の関係もないものである。概して卑猥なものが多く――“ヘッペ!”だの、“ヘッペコ!”だの、“ヘッペ落ちた!”だのの類である。
幌別に、いつも驚いた拍子に、“acika nepkor an-pe opataci”「汚いみたいなものが下痢した」とイムする男がいた。
名寄に、“e-cincimpoke sake kure ! ”「てめえのチンポに一杯のませろ!」とイムする男がいた。
これらの例でも分かる通り、何かに驚いた拍子に発する反射的な行動、叫び、またはその叫んだ文句をイムというのであるが、この場合のイムは、個人の感受性や刺激そのものの大きさによって多少程度の差はあっても、反応の経過は一過性であり、長く持続するということはないのが常である。
コタンカㇽカムイのイムというのがあって各地に伝承されている。それをここに紹介しておこう。「コタン・カㇽ・カムイ」kotan-kar-kamuy(コタンを・作った・神)については“参考3”に詳しく説く。
i)人間の始祖たる「コタンカㇽカムイ」――これは日本のダイダラボッチ、ダイダラボウシのごとく巨人に考えられている――がある日クジラをヨモギの串に刺して焼いていると、突然その串が折れて、クジラが火の中に落ちてジュウッと燃え上がったので、びっくりして尻餅をついた。その途端に次のようにイムしたというのである。胆振国幌別の伝承である。その尻餅をついた跡がOsorkot(“尻・跡”の義)という地名になって、白老郡竹浦村字アヨロにあり、そこの沖には、あたかも焼き串のぽっくり折れたような格好の岩が立っていると。
mokor humpe 眠っているクジラを
noya ari ヨモギの串で
ci-ma awa 焼いたら
o-imanit-ko-kay. 焼き串がぽっきり折れた。
rep ta an kamuy 沖にいる神
rehe tapne の名は
Hurekamuy ne フレカムイで
kim ta an kamuy 山にいる神
rehe tapne の名は
Sipasipa ne シパシパで
uko-kor poho その間に生まれた子
rehe tapne の名は
Rikuntuna- リクントゥナ
Haituna ne. ハイトゥナだ。
kotan osmak ta 村のうしろに
poro to an wa 大きな沼があって
horepasi 沖から
nise kusu yan-kur 水汲みに来る神
kamuy-sinta の航空船が
kurutun. 空にゆらゆら。
okimun 山から
nise kusu san-kur 水汲みに来る神
kamuy-sinta の航空船が
kurutun. 空にゆらゆら。
hai ku-ramu ! ああ驚いた!
沖という語は、家の中では炉の中心部を言う。そこにいる神の名の「フレ・カムイ」というのは“赤い・神”ということで、火をさすのである。山にいる神の名は、おそらくSuwat-suwatが訛って「シパシパ」になったので、suwatは鍋を吊るす自在のこと。その間に生まれたという子の名「リクントゥナ・ハイトゥナ」はrikun tuna hai tuna“上方の火棚・痛い火棚”の義である。sintaというのは、揺りかごのことで、それを天井から縄で吊って、その上に赤児を寝かせて縛りつけ、それを老婆が前後に押して揺り動かしながら
mokor sinta ねんねのおふねが
ran ran 降りたぞ降りたぞ
hoo cipo そらこげ
hoo cipo そらこげ
などと子守唄を歌ってあやすものである。アイヌはそれを舟と考え、古謡の中では神々がこれに乗って空中を航行すると語られている。従来それを神駕などと訳していたが、それはsintaに対するアイヌの気持ちを知らないものである。樺太の英雄詞曲ではそれをsarampe-pon-cih(p-i)“絹布の・小・舟”とも称する。全体の意味は、家の中で魚を焼いていたら、焼き串が折れて、魚が火の中にころげ落ち、ジュウッと燃え上がって、自在の縄に火がついた。びっくりして飛び上がったら、上の火棚にいやというほど頭をぶっつけた。人々が駆けつけて、水樽から水を汲んで来ては掛け掛けしてやっと火を消し止めた。火棚がまだ宙にゆらゆら揺れている。ああびっくりした!――というような意味と思われる。
次に掲げるのは、いずれも北見の美幌に伝えられていたものである。
ii)サマイクㇽ――これについても“参考3”に説く――が弓を仕掛けていると、突然弦がぷっつり切れた。びっくりした拍子に次のようにイムした。
opasi an kur 川下にいる神は
Suwasuwa ne ike スワスワであって
ya-ke wa an kur その岸にいる神は
Toncikama ne ike トンチカマであったが
uko-uturu その中間に
poro to onne to 大きな沼古い沼が
an wa ne ike あったのに
tu-suy pa ci-aunke 二度頭をつっこみ
re-suy pa ci-aunke 三度頭をつっこみ
hutatawe ! ああびっくりした!
ここでスワスワというのは、枝がたくさんついたまま立木を切って来て、その枝の先を適当の長さに切りつめ、それを家の前に立てて、肉やその他の物を掛けて干すものである。樺太でもそれがあって「ラッカイ」rahkayと言っている。トンチカマは“敷居”のこと。沼というのは庭をさす。びっくりした拍子に戸口に駆けて行って出たり入ったりしたというのである。
iii)これもやはり、サマイクㇽが弓の弦の切れた際にびっくりして発したイム。
raykur ! raykur ! 「ちきしょうめ! ちきしょうめ!」
osirpenan kotan そう叫んだ声が
o-aw-sitayki. 川上の村までとどいた。
osirpenan-kur 川上の酋長が
o-so(y)-o-terke 戸外へ飛び出して
o-itak awe 言ったことは
ene an-i: こうである――
tan-pa-an-pa 「今年という年は
nekona an 何て間の悪い
pa ne kusu ? 年だろう?
Oisokotkur 幸もち彦が
o-iso-kot kun 幸をもつなら
manu kusu sir-ki ! あんなことは言うまいに!」
ani hawki kane と言いながら
aw-o-terke. 家の中へ駆け込んだ。
hutatawe ! ああびっくりした!
(参考3)上記イムの主人公である「コタンカㇽカムイ」および「サマイクㇽ」について、従来その正体を突っ込んで説明したものがないので、ここで要点だけ説明しておこうと思う。
コタンカㇽカムイというのは、Kotan-kar-kamuy“コタンを・造った・神”という意味で、この世に初めて人間のコタンを造って人間文化の基を開いた神である。“arke kamuy arke aynu”「なかば神なかば人」とも形容され、別名を「アイヌラックㇽ」(Aynu-rak-kur“人間・くさい・神”の義、これを従来「人間臭い人」とか「人間くさいおかた」とか訳したのはkurの原義をつかめなかったからである)、あるいは北見地方で「オアイヌオルㇱクㇽ」(O-aynu-orus-kur“そこから・人間が・殖えた・神”“人間の始祖である神”の義)とも言われる。「ワリウネクㇽ」(Wariwnekur)とも言われるが、語源はo(そこから)-uware(皆が繁殖した)-iw(者)-ne(である)-kur(神)で、やはり“人間の始祖たる神”の義である。「オイナ」(oyna)と称する神謡の主人公として出て来るので「ア・エ・オイナ・カムイ」(A-e-oyna-kamuy“我らが・それについて・オイナに語る・神”の義、従来これを「我等の言い継ぎ語り継ぐ神」「我等の伝承する神」などと訳したのは不当であって、oynaには言うがごとく「古く伝承する」「古くより言い伝える」「語り継ぎ言い継ぐ」などという意味はどこにもないのである)とも言われ、また「オイナ・カムイ」(Oyna-kamuy“オイナする・神”の義、従来これをアエオイナカムイの省略形として「同じことを短くオイナカムイとだけいうこともある」と言っていたのは失当であり、むしろこの方がより古いと考えられる)とも言われる。oynaの原義は、tusuというのと同じく、“巫術”“巫術を行う”“巫に入って託宣する”ということで、神謡の一部はそういう託宣から発達したので「オイナ」と称せられるに至ったのである。従って「オイナ・カムイ」の原義は、“託宣する神”だった。北海道の中東北部から樺太へかけて「オイナ・カムイ」のことを別に「サマイクㇽ」「サマイェクㇽ」「サマイェカムイ」などというが、それらの語源は次のごとく解せられる。
i)Samaykur <Samayekur.
ii)Samayekur < samay-ye-kur < saman-ye-kur “シャマンを・言う・神”
iii)Samayekamuy <samay-ye-kamuy <saman-ye-kamuy“シャマンを・言う・神”。
以上いずれも「オイナ・カムイ」(託宣する神)の原義と符節を合わせたように一致している。日高の沙流地方ではそれを「オキクㇽミ」(Okikurmi)と言うが、それはo(裾)-kiki(きらきらする)-ur(皮ごろもを)-mi(着ている)と解せられ、やはり、シャマンの服装を思わせる。胆振の「オキキリムイ」(Okikirmuy)、石狩・十勝・釧路・北見等でいう「オキキリマ」(Okikirma)などは、「オキクㇽミ」から転訛した名である。
さて、従来、神謡の起源については、全く一元的に、神が巫者に懸って言わしめた託宣の歌から発達したと言われていた。けれども、それはあまりに固陋(ころう)な見解である。もちろん託宣から発達した神謡もあるけれども、そればかりでなく、もと祭儀の際に演じられる習いだった原始的舞踊劇において、巫者が神に扮して所作しながら、その所作を一つ一つ言葉に表して歌って行った、その歌謡から発達したものもあって、その方がむしろ重大なのである。
いわゆるユーカラ(「ユカㇽ」yukar)という語が、英雄詞曲(yukarを英雄叙事詩と訳すのは文体に即しすぎている嫌いがあって感心しない)をさすことになったのは後のことで、その前は神々の詞曲、すなわち神謡がyukarだった。そのyukarには“真似る”という意味があって、現にいくらでもその例にぶつかるのである。そしてその語源にさかのぼればyuk-kar“獲物を・つくる”“獲物を・なす”ということだったと思われる。
今の熊祭りやフクロウ祭りの前身は、出猟前の季節祭だった。冬になって山入りの時が近づくと、あらかじめ猟運を確保しておくために、盛大な祭を行った。その祭において、巫者が獲物たる動物――アイヌにおいてはそれが神である――に扮する、――例えば彼は屋内の壁際にかけてあった熊の皮を頭からかぶる、すると彼はたちまち熊になる、そして熊らしく“hu-wee! hu-wee!”とか“o-wee-we hum!”とか言って鳴きながら場内に出て来て、舞を舞う。その舞において、冬ごもりの穴から出て来た熊が山を彷徨しているうちに人間の狩人の手に討ち取られるに至る経緯――それを神が天国の自分の家を出て肉を手みやげに人間の里を訪れ、気に入った者を見つけてその者のもとに“客となる”というふうに所作で表すと同時に、その所作の一つ一つを言葉で表して歌う。その歌が後に神謡にまで発達したのであって、神謡のリフレイン(「サケヘ」sakehe)の本源的なものに動物の鳴き声が多いのもそのためである(知里真志保、銀のしずく降れ降れまわりに、北海道郷土研究会刊行、注解(5)、p.18〜19参照)。
その時の巫者の扮装、すなわち初めは熊の皮をかぶって熊になったのが、後に象徴化して、「サパウンペ」(sapa-un-pe“頭・の・もの”、南部方言)「パウンペ」(pa-un-pe“頭・の・もの”、北部方言)あるいは「イナウル」(inaw-ru“幣の
頭髪”)と称する礼帽に残っている。すなわち酋長の頭に頂く礼帽の前頭部に熊やフクロウの木彫のついているのがそれである(上掲、銀のしずく、注解(11)、p.20参照)。
アイヌの酋長は、古くさかのぼれば巫者であった。巫者は神と人との中間に立つ者である。すなわち“なかば神なかば人”である。昔の酋長が「ウラㇱペトゥンクㇽ」(Uraspet-un-kur“ウラㇱペッの里の神”の義)とか「ユペトゥンクㇽ」(Yupet-un-kur“湧別の里の神”とか呼ばれたのは、それが「アイヌラックㇽ」(人間くさい神)だったからである。酋長たる巫者は、祭において神に扮して演戯したり託宣したりする者であった。すなわち「オキクㇽミ」(裾のきらきらする皮ごろもを身に着ける者であり、「サマイクㇽ」(巫術して託宣をいう神)であり、オイナカムイ(託宣する神)であった。
かくして、コタンカㇽカムイの正体は、古代社会における巫者に他ならなかった、ということが結論されるのである。→補注(23)
(参考4)コタンカㇽカムイの国造りに関して、次のような伝説が幌別に語られていた。
太古、コタンカㇽカムイがコタンを造った際、人間の隠し所をどこに設置すべきかに迷い、カワウソを派して天神の神意をうかがわしめた。天神が思うには、“カワウソという奴はひどく忘れっぽいから、ありのままに言えばアベコベに伝えるだろう。だからひとつアベコベに言ってやろう!”そう考えたので、“人間の隠し所は前額部に置くに限るよ”と教えた。カワウソはかしこまってコタンカㇽカムイのもとへ戻って来たものの、天神の教えたことなどケロリと忘れて、“人間の隠し所は股間に置くに限ると申されました”と復命した。コタンカㇽカムイは“いかにも!”と思い、その通りに人間を造った。おかげで、今の人間は、恥ずかしい思いをせずに暮らすことができるのである(知里真志保、アイヌ民俗研究資料第一、pp.7〜8)。
すでに見たように、コタンカㇽカムイは巫者だった。その巫者に使われて神意を伺いに行ったのがカワウソだったのには意味がある。カワウソはもともと、海のカワウソと言われるラッコと共に、巫者の有力な憑き神だったと思われるからである。カワウソが物忘れすると一般に信じられているのも、巫術における放心状態と無関係ではあるまい。→補注(24)
胆振の幌別では、カワウソの頭の煮たのはすこぶる賞味されたが、それを食う際は、あらかじめ山行きの服装をととのえ、荷縄やナタの類に身をかためて、それから食うのが習いであった。そうしなければ、何か肝心なものを忘れて、山へ行ってからまごつくからだという。これはしかし後からの解釈であって、もとは巫者がカワウソの頭骨を削り花に包んで秘蔵し、卜占の際などにそれを取り出して用いたからであり、そういう際には必ず巫装を整えてすべきものだったことを示すものである。
カワウソはもと「チロンヌㇷ゚」cironnupと言われたらしい。胆振の礼文華ではそれをwor-un-cironnup「水中の獣」、北見の美幌ではwor-us-cironnup「水中にどっさりいる獣」と言っている。しかし、樺太・北海道を通じてどこでも用いられるのは、「エサマン」という語である。esamanは、esamankiの下略形である。esamankiは、バチラー辞書によれば、カワウソの頭骨をもってする卜占だとあり、原義はe-saman-ki「それで・シャマンを・する」であったと思われる。ところがesamanの意味が忘れられるに及んで、民衆の語源意識はそれをesaman-ki「エサマンを・する」と分析し、この卜占にはカワウソの頭骨が多く用いられたところから、esamanがカワウソの意に解されるに至ったものと思われる。
樺太アイヌは、その北方の隣人であるギリヤク・オロッコ・トゥングスなどからシャマニズムを取り入れて、それをsamanと言っている。この語は北海道ではすでに廃用に帰してしまったけれども、その痕跡だけは、前記サマイクㇽの名称及びこのカワウソの名称の中に見出されるのである。→補注(25)