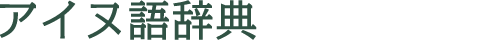植物編 §298 ハルニレ Ulmus Davidiana Planch. var. japonica Nakai
(1)cikisani チキサニ [ci(我ら)kisa(こする)ni(木)] 茎 ⦅全北海道⦆
注1.――この場合のkisaは“こすって火を出す”の意。
(2)cikisan-ni チキサンニ [<cikisani] 茎 ⦅美幌、屈斜路⦆
(3)kara-ni カラニ [kara(発火器)-ni(木)] 茎 ⦅白浦、真岡⦆
注2.――北海道でも、北見国宗谷郡に「カラニタナイ」karani-ta-nay“アカダモ・とる・沢”)(C、p.425)、同じく紋別郡に「カラニオマナイ」(karani-oma-nay“アカダモ・ある・沢”)(C、p.455)等の地名がある。
(4)nikap ニカㇷ゚ [ni(木)kap(皮)] 樹皮 ⦅胆振、日高、天塩⦆
(5)nikap-at ニカパッ [nikap(樹皮)at(樹皮から取った繊維)] 内皮から取った繊維 ⦅幌別⦆
(6)pon-at ポナッ [pon(小さい)at(繊維)] 内皮から取った繊維 ⦅美幌⦆
注3.――at(オヒョウの繊維)よりも品質が劣るのでpon(小さい)という限定詞を冠する。
(7)ponat-ni ポナッニ [ポナッをとる木] 茎 ⦅美幌⦆
(参考)この木から取った繊維は、そう強くないから、織物としては使用しなかったが、織物に模様をつけるために織り込まれるし、細く裂いて乾かした皮を噛んで柔らかくして、「ケルルンペ」kerurumpe[keri-or-un-pe 靴・の中・に入る・もの]と称する靴下のようなものを作った(美幌、屈斜路、天塩)。胆振・日高でも、ござに模様をつけるために、この繊維を織り込むが、それを「オニカプンペ」onikapumpe[<o-nikap-un-pe そこに・ハルニレの繊維・入っている・もの]と称する。
また、前条のオヒョウニレの場合と同様の工程によって、この樹皮から精製した繊維で布を織り、背負い鞄や手提げ鞄など種々の袋物を作るし、今はしないが、昔はこれで衣服を作ったらしく、それを「ニカパットゥㇱ」(nikap-attus ハルニレの繊維の・厚司)と言い、神話の中で人祖アイヌラックル(Aynurakkur)が出かける時は、いつも裾のこげたハルニレの厚司衣(o-uhuy-nikap-attus)を着て、尻のこげた刀鞘を佩びたと伝えられている。
アイヌラックルの父は日の神とも雷神とも疱瘡神とも言われ、土地により人によっていろいろに伝えられているが、母は常にハルニレ姫である。
ある神話によれば、ハルニレ姫は天界にも稀な美しい女神であったので、雷神はそれに見とれているうちに、つい足を踏み外してハルニレ姫の上に落ちてしまう。そのためハルニレ姫は身ごもってアイヌラックルを生むが、ハルニレの梢は風当たりが強く、子供を育てることが出来ないので、自分の皮で着物を作って着せ、抜けば火の燃える剣を与えて、天界の造化の神のもとで成人した後に、再び人間界に下って、人間生活の基を開いたというのである(金田一京助、アイヌの神典、p.20)。
ハルニレ姫が自分の皮で子供に着物を作って着せたとある所に、この木の皮を衣料に用いた古俗の反映が見られる。また、父が雷神で母がハルニレでその間に生まれたアイヌラックルの服装が裾の燃えている厚司衣だとか、尻の燃えている刀鞘だとか、抜けば火の燃える剣だとかいうのは、落雷による地上の火の起源を暗示し、かつハルニレの木を用いて発火した古俗を反映している。
火の創造に関して種々の神話が伝承されているが、そのいずれにもハルニレが関係していることは、その意味において注意される。次にその主なものを掲げる。
Ⅰ. 造化の神(「コタンカㇽカムイ」Kotan-kar-kamuy「世界を・造った・神」)が世界を造った時、真っ先に生えたのがドロノキで、次に生えたのがハルニレであった。造化の神が人間に火を授けようとして、まずドロノキで発火台(「カㇽソ」kar-so「発火器の台座」)と発火棒(「カッチ」katci<kar-ci「発火器の陰茎」)を作り、それを揉んで火を起こそうとしたけれども、いくら揉んでも白と黒の揉みくず(「カㇽパㇱ」kar-pas「発火器の炭」)が溜まってくすぶるばかりで、火はついに出来なかった。いまいましくなって白い揉みくず(「レタㇽ・カㇽパㇱ」retar-karpas「白い発火器の炭」)(燠の上にできる白い粉を普通に「レタㇽ・パㇱ」という)を吹くと、ぱっと舞い上がって「パウチカムイ」(pawci-kamuy「淫乱の神」)という魔神になり、黒い揉みくず(「クンネ・カㇽパㇱ」kunne-karpas「黒い・発火器の炭」(黒い消し炭を普通に「クンネ・パㇱ」という)を吹くと、「パコㇽカムイ」(pa-kor-kamuy「疱瘡の神」〔これは現実には渡り鳥の姿をとる〕)となって飛び去った。だから「パコㇽカムイ」は、人間世界に長たる貴い神であるけれども、短気で怒りっぽいのである。ドロノキで作った発火台と発火棒とは、それぞれ「ケナㇱウナㇽペ」(kenasi-unarpe「木原の伯母」〔現実にはミミズクに似た怪鳥として現れる。知里真志保、アイヌ民族研究資料第二、p.75)〕と、それから「イワエトゥンナイ」(iwa-etunnay〔現実にはやはりくちばしのとがった怪鳥の姿をとる〕)とよぶ恐るべき魔神となった。ドロノキで失敗した造化の神は、今度はハルニレの木で発火台と発火棒とを作り、それで揉むと初めて「アペ・フチ」(ape-huci「火の婆」)が生まれた。すなわち火が生じた。だから我々はこの木を「チ・キサ・ニ」、すなわち「我々が火を揉み出す木」と呼ぶようになったのである。この時生じた白い揉みくずは、飛んで「ハシナウ・ウㇰ・カムイ」(hasinaw-uk-kamuy「枝幣を・取る・神」〔山幸を恵む神、狩りの女神、現実にはカケスなどのごとき小鳥の姿をとる〕)となり、発火棒は化して「ヌサ・コㇽ・カムイ」(nusa-kor-kamuy「屋外の幣場を支配する・神」〔現実には蛇の姿をとる〕)となった。こうしてハルニレから生じた火の神・狩りの神・幣場の神は互いに姉妹に当たる貴い神として、日常我々が礼拝するようになった。また、ドロノキは憑き神(「カㇱカムイ」kas-kamuy)の拙い木であったから、この木から生じた神々はすべて魔神で、我々は日常木幣を捧げて礼拝することはしないのである。ただ疱瘡神が巡行して、「ハルエカムイノミ」(haru-e-kamuy-nomi 供物を疱瘡神に捧げてこれを去らせる祭儀)を行う時だけは、その姉妹に当たる火の婆神や幣場の神に祈って、人間に代わって疱瘡神をなだめてもらうのである(日高国沙流郡平取村・平村コタンピラ翁の伝承――知里・久保寺「アイヌの疱瘡神パコロカムイについて」)。以上を表示すれば、次のようになる。
I.
1. yay-ni(ドロノキ)
(1) retar-karpas…………pawci-kamuy
(白いもみくず) (淫乱の神)
(2) kunne-karpas…………pakor-kamuy
(黒いもみくず) (疱瘡の神)
(3) kar-so…………………kenas-unarpe
(発火台) (木原の怪鳥)
(4) ketci……………………iwa-etunnay
(発火棒) (奥山の怪鳥)
2.cikisa-ni(ハルニレ)
(5) retar-karpas…………hasnaw-uk-kamuy
(白いもみくず) (枝幣の神)
(6) ……………… …………ape-huci
(火の神)
(7) katci……………………nusa-kor-kamuy
(発火棒) (幣場の神)
Ⅱ. 造化の神が世界を造った時、まずドロノキで発火台と発火棒を作って揉んだ。その際、白いもみくずからは「オリパㇰカムイ」(oripak-kamuy「恐ろしい神」〔疱瘡の神〕)が生まれ、黒いもみくずからは「イペルスイチカㇷ゚」(iperusuy-cikap「空腹の鳥」〔アホウドリ〕)が生まれた。発火台は「モシㇼシンナイサㇺ」(mosir-sinnaysam「世界のばけもの」という魔神となり、発火棒は「ケナㇱウナㇻペ」(kenas-unarpe「木原の伯母」)という魔神になった。けれども、ついに火は燃えなかった。次にハルニレで発火台と発火棒を作ってもむと、白いもみくずからは「枝幣の神」(狩りの神)が生まれ、黒いもみくずからは「キムンカムイ」(kim-un-kamuy「山・の・神」〔熊〕)が生まれ、そして火が燃え出した。発火台は「幣場の神」(産土・農業神)となり、発火棒は「キナスッカムイ」(kina-sut-kamuy「草の根元の神」〔ヘビ〕)となった。ドロノキから生まれた魔神たちは兄神であり、ハルニレから生まれた善神たちは弟神に当たるが、互いに悪口を言い合い喧嘩ばかりして仲が悪いのである(日高国沙流郡二風谷村・二谷国松翁の伝承――知里・久保寺「上掲論文」)。以上を表示すると、次のようになる。
II.
1. yay-ni(ドロノキ)
(1) retar-karpas…………oripak-kamuy
(白いもみくず) (疱瘡の神)
(2) kunne-karpas…………iperusuy-cikap
(黒いもみくず) (アホウドリ)
(3) kar-so…………………mosir-sinnaysam
(発火台) (世界のばけもの)
(4) katci……………………kenas-unarpe
(発火棒) (木原の怪鳥)
2.cikisa-ni(ハルニレ)
(5) retar-karpas…………hasinaw-uk-kamuy
(白いもみくず) (枝幣の神)
(6) kunne-karpas …………kimun-kamuy
(黒いもみくず) (山の神――クマ)
(7)……………………………ape-huci
(火の神)
(8) kar-so…………………nusa-kor-kamuy
(発火台) (幣場の神)
(9) katci……………………kina-sut-kamuy
(発火棒) (草の根元の神――ヘビ)
Ⅲ. 造化の神が世界を造った時、国土の西の方でまずドロノキが生え、ついでワラビが生えた。次に国土の東の方でハルニレがまず生え、それからヨモギが生えた。造化の神が人間に火を授けようとして、まずドロノキで発火棒と発火台を作って揉むと、白と黒の揉みくずが出来た。造化の神がその白い揉みくずを吹くと飛び散って淫乱の神となり、黒い揉みくずを吹くと飛び散って疱瘡の神となった。その黒い揉みくずのうち、特別大きなのが海中に落ちてアホウドリの神となった。しかも、ついに火は出なかった。造化の神の手づくりの品は、そのまま土と共に腐ってしまうのがもったいないので、ドロノキで作った発火棒と発火台はそれぞれ奥山の怪鳥と木原の怪鳥になった。造化神は、今度はハルニレで発火棒と発火台を作って揉むと、白いもみくずと黒いもみくずとが出来た。白いもみくずを吹くと飛び散ってオオカミ神となり、黒いもみくずは枝幣の神となった。さらに揉んでいると、ついに火の神が生まれた。造化の神の手づくりの品は、何によらずそのまま土と共に腐ってしまうのはもったいないので、ハルニレの発火棒と発火台はそれぞれ幣場の神と山の神になった。こうして国土の西の方のドロノキから生まれた魔神たちは、国土の東の方でハルニレから生まれた善神たちよりも年上の神であるのに、造化の神が弟神を木幣を受ける神(inaw-uk-kamuy)として優遇したので、それを快く思わぬ西方の魔神たちが、ドロノキから生まれた神々に味方して、昼となく夜となく造化の神の城を攻めたてた。造化の神は東方の神々を動員してそれに当たらせたが、連戦連敗で悪戦苦闘したが、最後に東方に草としては最初に生まれたヨモギで人の形を作って戦に出し、それによってやっと勝つことができた。このヨモギで作った神は「イモㇱカムイ」(imos-kamuy→§1“参考2”)「アイヌ・モンカ・エ・ヌプル・カムイ」(aynu-mon-ka-e-nupur-kamuy同上)「アイヌテケカルカムイ」(aynu-tek-e-kar-kamuy同上)などと呼んでいる。この神戦に出る時は黒い小男の姿になる(日高国沙流郡平取村の伝承――名取武光「沙流アイヌの熊送りにおける神々の由来とヌサ」北方文化研究報告第四集)。これを表示すれば、次のようになる。
III.
1. yay-ni(ドロノキ)
(1) retar-karpas…………pawci-kamuy
(白いもみくず) (淫乱の神)
(2) kunne-karpas…………pakor-kamuy
(黒いもみくず) (疱瘡の神)
〃 …………siratki-kamuy
(アホウドリの神)
(3) kat-ci……………………iwa-etunnay
(発火棒) (奥山の怪鳥)
(4) kar-so……………………kenas-unarpe
(発火台) (木原の怪鳥)
2.cikisa-ni(ハルニレ)
(5) retar-karpas…………horkew-kamuy
(白いもみくず) (オオカミ神)
(6) kunne-karpas…………hasinaw-uk-kamuy
(黒いもみくず) (狩りの神)
(7)……………………………kamuy-huci
(火の神)
(8) katci……………………nusa-kor-kamuy
(発火棒) (幣場の神)
(9) kar-so……………………kimun-kamuy
(発火台) (熊神)
Ⅳ.国土創造の神が国土を創造した時に、初めて地上に生じたのはハルニレであった。その次はヨモギであった。次はワラビであった。国土を作り終えた神が一休みをして火を焚こうとした時に、最初にヨモギをもんで燧(ひきり)に用いた。ヨモギはいくらもんでももんでも火が出なかったから、吹いたら飛んで鳥の群れとなって行った。行って行ってそれがついに疱瘡神になったのである(日高国沙流郡平取村・平村コタンピラ翁の伝承――金田一京助、アイヌの神典、p.19)。
Ⅴ.この世の初めに神がドロノキを生やして下すった。アイヌはそれで火を起こそうとして「カㇽキシャ」(kar-kisa 木と木と摩擦して火を起こす方法)したが、いかに努力しても煙ばかり出てついに火は起こらなかった。そこでドロノキと煙は嫌われて遠ざけられた。次にこの世に現れたのはハルニレである。この木でカㇽキシャしたら直ちに火が起こった。アイヌはこの火を「カムイフチ」(kamuy-huci「神なる婆さん」)とたたえ、最高の神として尊敬するようになった。先にドロノキから生まれた煙はすこぶる不平でこれをねたみ、ついに疱瘡病の神となって人に災いを与えるようになった。疱瘡の神をパコㇿカムイ(pa-kor-kamuy「煙を・もつ・神」)というのはこの故である。火の神は疱瘡の神の妹であるから、流行病の話などは炉端ではしないことになっている。それは火の神が人に対して気の毒がられるからである。なお、流行病の時はドロノキは炉にくべないことになっている(胆振国白老村の伝承――満岡伸一、アイヌの足跡)。
以上火の創造に関する神話にはどれもハルニレが関係しているのは、すでに述べたように、この木を用いて発火した古俗がそこに反映しているのである。
コタンにマッチ(「チケンキ」cikenki)が入る以前の発火法は、主として火打によったようであるが、それを北海道では「ピウチ」piwciと言い、名称からも直ちに察せられるごとく、日本渡来のものである。それ以前のアイヌの発火法に、木の板に穴をあけてそれを発火床(kar-so“発火器の・床”)とし、その上に発火棒(katci、<kar-ci“発火器の・陰茎”)を垂直に当てがって、その上端を両手に挟んで錐をもむようにしてもみ、その摩擦によって火を起こしたのである。松浦竹四郎の『久摺日誌』にその図が載っていて、次のような説明がついている。“能く乾たる椴の木か獮𤠣桃の木か赤たもの木の久しく水に浸り晒れたるを以て揉む時は上下熱して火出るなり、其木口を吸は火燃出すなり。それを樺皮に附るなり”。
日高の沙流では、発火棒の上端に貝殻をのせて左手で押さえ、発火棒の中央に弓の弦を巻いて、その弓を右手で前後に動かすことによって発火させる方法を用いた。
北見の美幌では、山中で火打がない時、ハルニレの立ち枯れ(ci-ni)から割り木(ci-perpa-ni)を一本取って、その一端を腹に当て他端を前方の何かに当てて突っ張る。別にイタヤカエデの枯れた手頃の棒を見つけて、ハルニレの割り木に直角に当てがい、その両端を両手に握って、砥石で物をとぐような具合に前後に摩擦して発火させる方法があった。それを「シルピ」sirupiと言った。siru-piwci(こする・火打)の下略である。
このように、発火器の材料としては、発火しやすい木なら何でも用いたらしいが、特に用いられたのはハルニレの木だったらしく、この木の名称がそれを示している。すなわち、cikisaniは“我々がこすって火を出す木”の義であり、kara-niも“発火器にする木”の義である。ついでながら、kara(樺太)kar(北海道)は“火をきり出す”という意味の動詞ではない。もしそれならば、木の名は、アイヌ語の語形成法及び植物命名法の常則から見て、ci-kara-niあるいはci-kan-niとならなければならぬはずである。kara及びkarは、実は名詞であって、発火器を意味する。北海道で発火台をkar-so(「発火器の・床」)、発火棒をkatci(<kar-ci「発火器の・ちんぼ」)、もんでいる際に生じる燃えくずをkar-pas(「発火器の・炭」)、この発火台の上で発火棒をもんで火を出すことをkar-kisa(「発火器を・もむ(または、こする)」)、火打道具を入れる袋をkarop(<kar-o-p「発火器・入る・もの」)というのは、皆それである。
樺太では錐揉み法による発火器をikisah(<i-kisa-p「それを・きり出す・もの」)というのに対し、karaは今はもっぱら火打をさすようである。火打袋をkaroh(<karop、<kar-o-p「発火器、入る・もの」)、火打石をkahsuma(<kar-suma「火打の・石」)、火打で火を打ち出すことをkahta(<kar-ta「火打を・打つ」)という。
ハルニレはまたその根を乾かしてほくちにもした(菅江真澄)。
なお、ネブトが出た場合に、ハルニレの若枝を噛んでつけると破れるから、その後へオオバコかカブラの葉を貼って膿を吸い出した(幌別)。
十勝地方では、内皮を洗髪に用いた(アイヌの髪容、p,63)。