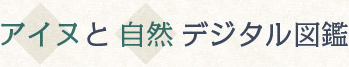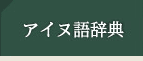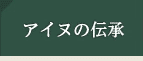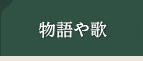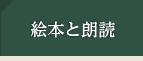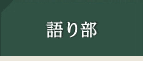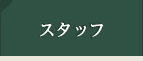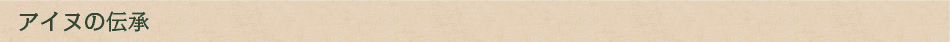| ID | 伝承者 | 日本語名 | 伝承者の アイヌ語名 /日本語名 |
伝承 |
|---|---|---|---|---|
| 1056 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0122 ウド |
【ア】チマキナ 【日】ウド |
・芽吹きの頃、茎の皮をむいて刻んで水にさらし、野草の汁物に入れました。火を止める直前に刻んだ葉も入れて食べました。34178 ・頭がかぶれてかさぶたがたくさんできたときや、大きな怪我をしたときに、葉を焼いて貼りつけました。これは毒を抜く薬だといいます。また根を煮て、その煮汁を冷ましたもので傷を洗い、中の芯を取ってほぐしてから傷に貼りつけました。34121,34135,34142,34178,34445 |
| 1057 |
 平取町
平取町 |
P0122 ウド |
【ア】チマキナ |
・傷のうみを取るのに、ウドの根を煮て、柔らかくなったら皮をむいて中の芯を取り、傷に押しつけました。35003,35004,35009 |
| 1058 |
 平取町
平取町 |
P0122 ウド |
【ア】チマキナ 【日】ウド |
・茎は花が咲く前、かなり大きくなったものを煮て皮を剥いて食べました。34647,34715 ・根は薬にしました。煮たものの皮をむき、芯を取ってから手のひらで薄くし、頭がかぶれてかさぶたができた子供の頭に貼りつけました。そうすると悪い汁を吸い出して、ばい菌が入らないのだといいます。34647,34729(34646) ・保存して冬に食べたり薬にするということはしませんでした。34713 |
| 1059 |
平取町 |
P0122 ウド |
【ア】チマキナ 【日】ウド |
・長く伸びた茎を切って鍋で煮て、皮をむいて食べました。35306,35267,35280 |
| 1060 |
P0122 ウド |
【ア】チマキナ 【日】ウド |
・煮汁をできもののうみを取るための湿布に使いました。 | |
| 1061 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0125 ハリギリ、センノキ |
【ア】アイウㇱニ 【日】センノキ |
・大きくなったときのアイヌ語の名前はわかりませんが、ノコギリで切ると、とても切りやすいやわらかい木でした。34109(34101,34131,34152) ・この木で臼を作りました。34443 |
| 1062 |
 平取町
平取町 |
P0125 ハリギリ、センノキ |
【ア】アユㇱニ 【日】セン センノキ |
・おじいさんが若いとき山に行くと、コノハズク(=鳥名)が後からついてきてずっと鳴いていたそうです。気味が悪いので「とげの生えた木」を声のするほうに振り上げました。しばらく声は止むものの、またしばらくすると鳴いてついてきます。でも何とか木のおかげで無事に帰ることができたということでした。34685 ・センノキを火にくべると、大きくはねて遠くまで飛ぶので、まきには使いません。34685,34671 |
| 1063 |
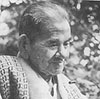 帯広市
帯広市 |
P0125 ハリギリ、センノキ |
【日】センノキ |
・お盆やテーブルを作りました。柔らかくて折れやすく、製品にした後の狂いがなく良い木です。30109A |
| 1064 |
 むかわ町
むかわ町 |
P0139 シナノキ |
【日】シナ |
・人から頼まれて、大鍋でシナノキの皮を煮たことがあります。でもすすがついてあまりうまくいきませんでした。35245 |
| 1065 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0139 シナノキ |
【ア】ニペㇱニ ポンニペㇱ 【日】シナ シナノキ |
・皮を剥ぐのは6月です。34104 ・皮は[一部ではなく]全てはぎます。若木の樹皮(内皮)をとって糸を作ると、やわらかくて丈夫な糸ができます。太くなった木から作った糸は切れやすいのです。作った縄で、家の屋根や壁のカヤをしばったり、荷物をしばったり、馬をつなぐのに使いました。34101 →口承文芸資料「シナ皮を背負ったクマ」34126,34146 ・糸を作る方法は、沼につけておく方法もありますが、それをせずに灰を入れて煮て作った糸が一番丈夫です。34147 ・シナノキで作った糸は水がかかっても切れずに丈夫です。34121 |
ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
本文ここまで
ここからフッターメニュー