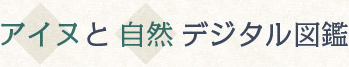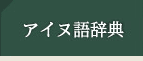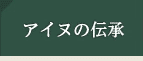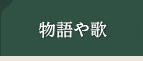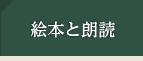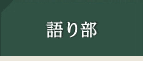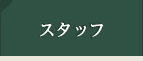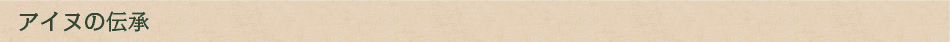| ID | 伝承者 | 日本語名 | 伝承者の アイヌ語名 /日本語名 |
伝承 |
|---|---|---|---|---|
| 1076 |
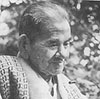 帯広市
帯広市 |
P0146 イタヤ イタヤカエデ |
【ア】トペニ 【日】イタヤ |
・昔は春先に山へ行き、この木の南側の氷がとけたところになたで削り、出て来る樹液を飲みました。30109 ・この木で神へ祈るときに使う捧酒箸を作りました。 |
| 1077 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0153 ツルウメモドキ |
【ア】ハイ(プンカㇻ) |
・3月頃、堅雪の上で雪ざらしにします。34102 ・糸にしてござ編みの糸にしましたが、麻の糸が店で売られるようになってからはそちらを使うようになり、ツルウメモドキをとることもなくなりました。34138 ・サケ皮の靴を縫うときも、丈夫なこの糸を使いました。34156 ・弓の弦、下帯など肝心なところに使いました。34163 |
| 1078 |
 平取町
平取町 |
P0153 ツルウメモドキ |
【ア】ニカウンハイ ハイプンカㇻ |
・3月頃堅雪の上を歩いてとりました。丈夫で軽くて柔らかい糸ができます。雪ざらしは、内皮を鍋で煮てから雪の上に並べました。むらに染まらないようにきれいに広げ、一週間もすれば真っ白に仕上がりました。34644 ・弓の弦や下帯、荷縄を作りました。下帯は地肌につけるので、ツルウメモドキの下帯はつけていることを忘れるくらいに柔らかいものでした。他の素材で作ったものはガサガサとして痛いのです。34644 |
| 1079 |
平取町 |
P0153 ツルウメモドキ |
【ア】ハイ |
・冬にとって来て、母親が糸を作りました。私はその横で大人のまねをして弓を作ったのを覚えています。35267 |
| 1080 |
P0153 ツルウメモドキ |
【ア】ハイプンカㇻ |
・糸を作りました。 | |
| 1081 |
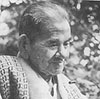 帯広市
帯広市 |
P0153 ツルウメモドキ |
【ア】フハイ 【日】 ツルウメモドキ |
・アカブドウと言って、皮をはいで編み袋を作りました。30109 |
| 1082 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0166 ヤマウルシ |
【ア】ウッシニ |
・漆にかぶれないようにするには、ヤマウルシの木に抱きついて揺すりながら「あなたを好きだけれど、あなたは木で私は人間。一緒にはなれないのです」という歌を歌います。そうするとかぶれることがないのだといいます。34102,34138 ・おじさんが家に入ってきて炉の火にあたっていると、「まるで漆にかぶれたようだ」と言って体中がかゆくなりました。多分私が知らずにヤマウルシをとってきて火にくべてしまったのでしょう。私はおまじないのおかげでかぶれないため、気がつかなかったのです。おじさんから「おまえ、漆をとってきたのではないか」と聞かれましたが、怒られるのが恐いので「知らない。漆って何?」と言ってとぼけておきました。34102 |
| 1083 |
 平取町
平取町 |
P0166 ヤマウルシ |
【ア】ウッシ |
・漆かぶれには、ヨモギの葉の汁をつけます。35007 |
| 1084 |
 新ひだか町静内
新ひだか町静内 |
P0172 キハダ カラフトキハダ |
【ア】シケㇾペ |
・実を煮物料理に入れて食べました。また実を煮詰めてあめのように煮詰めてから固め、肺病の薬にしました。34102 ・木の内皮はお湯で煮て、腹痛の薬として飲みました。また内皮を干して粉にしたものに酢を少し入れて混ぜ、布に塗って打ち身に貼りました。34102 ・おばあさんが小枝でくしを作り、髪をすいてくれました。34101,34182 |
| 1085 |
 平取町
平取町 |
P0172 キハダ カラフトキハダ |
【ア】シケㇾペニ 【日】シコロ |
・胃が痛いときに、樹皮(内皮)をお湯で煮てその汁を飲みました。35007 ・頭にかさぶたがたくさんできたときは、この木の樹液の入った水で洗いました。35008 |
ヘッダーメニューここまで
ここから本文です。
本文ここまで
ここからフッターメニュー